人の動きから、建築の「心地よさ」を分析する
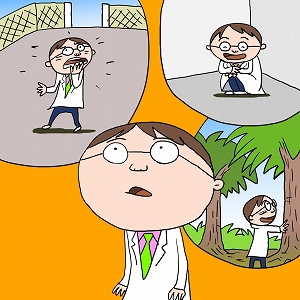
人の行動を左右する「エッジ効果」とは?
例えば広場のような、ひらけた空間に放り出された時、人はその空間の真ん中に立っているよりも、壁際や木陰など大きなもののそばに寄ったり、空間の周辺部分にいようとしたりする傾向があります。これを心理学では「エッジ効果」と呼んでいます。これは、人間が狩猟民族であった時代の名残ではないかと言われています。自分の姿がほかから見えにくく、かつ周囲を観察できる位置が、本能的にもっとも安心できる場所であるということです。
人間がある空間を移動したり、滞在したりする動きを「アクティビティ」と呼びますが、人のアクティビティは、このようなさまざまな心理的効果によって、無意識のうちに左右される場合があります。人の移動の多い場所では長時間滞在しづらいものですし、床材が柔らかい素材だと滞在時間が長くなるという調査もあります。
アクティビティの可視化で見えてくるもの
アクティビティは、快適な建築を設計するために大きな意味を持ちます。これまでの建築でも、人のアクティビティを意識する設計は行われてきましたが、それを実地で調査して数値化するなどの試みは多くはありませんでした。
実際の建築で人の動きや滞在時間、さらには視線の動きなどを調べて可視化していくことで、人が何を心地よいと感じるのか、という分析ができます。それにより、通路の広さや窓の高さ、家具の配置などについて、より「心地よさ」を感じられる設計が可能となります。
「心地よさ」の先にある都市の「豊かさ」
建築はそれ単体で成立するものではなく、周囲の環境からの影響を受けますし、周囲にも影響を及ぼす存在です。設計にあたっては、都市環境を意識したデザインが必要とされることになります。そうすることで、都市が建築を作り、建築が都市を作るといったフィードバックが成り立ちます。つまり、建築の「心地よさ」を追求していくと、都市全体が豊かになっていくと考えることもできるのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )

