人体は微生物の乗り物である
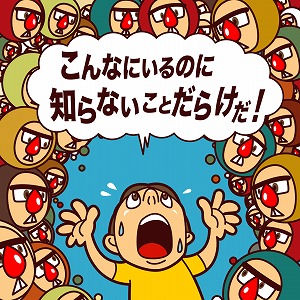
ほかの生物が住めない場所でも生きられる微生物
私たちの生活圏に存在するカビや細菌類はもちろん、深海や地底、成層圏に近い上空、マイナス数十℃の極寒環境から100℃を超える高温環境まで、地球上のありとあらゆる場所に微生物は存在していますが、現在の技術では、地球上に存在する微生物の、およそ1%しか培養できていないと言われています。
さらには1%のうち、なぜその環境下で生きているのか、どういう能力を持っているのか、はっきりわかっている微生物の数は、ほんのごく一部です。顕微鏡を使わないと観察できない、小さな微生物が持つ大きな力を解明し、私たちの生活にとって有益な活用法を探るのが、「応用微生物学」という学問です。
さまざまな分野で活用されている微生物の「力」
納豆や味噌(みそ)、ヨーグルトなどの発酵食品をはじめ、ペニシリンやワクチンなどの医薬品、農業用資材、工業用素材などで微生物の力が活用されています。微生物が有機物を分解する力で、海や土壌を浄化する研究も進んでいます。ただ、微生物全体から見ると、ごくわずかな種類を利用しているにすぎず、能力も活用法も未知の微生物が数え切れないほどいます。特に、深海や地底の微生物は、地表の数十倍もの水圧・地圧がかかっても変性しない特殊な細胞構造を持っているので、研究が進めば、想像もできない活用法があるかもしれません。
身近な素材から素晴らしい価値を生み出す
現代化学の基礎となった「錬金術」を知っていますか? ありふれた金属に何らかの処理を施すことで、金などの貴金属を作り出す試みのことです。応用微生物学の研究も、微生物を使って、泥や土、水、空気などのごく身近な素材から価値のあるモノ(効果)を生み出そうとする学問で、言うなれば「錬菌術」です。
極限的な環境ばかりでなく、人間と同じ生活環境にいる微生物の中にも、新たな活用法が期待されている微生物がたくさんいます。微生物の数だけ夢があるのが、応用微生物学の楽しさなのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )













