航空力学の進歩で、飛行機のカタチが劇的に変化するかも!?

変わらない飛行機の基本形状
20世紀初頭のライト兄弟による飛行から現代までの間に、飛行機にはさまざまな空力的な改良が加えられてきました。より大きな揚力(機体を持ち上げる力)を得るため、空気抵抗を減らすためなど、きりがないほどです。
ただし、細長い機体に主翼と尾翼が付いているという基本的な形状は、100年前からあまり変わっていません。プロペラ機であれジェット機であれ、従来の技術を使う限りにおいては、ほぼ最適な形状となっているからです。
ヘリコプタがドローンに進化
自動車の動力が、エンジンから電気モータに切り替わりつつあるように、航空機の世界でも、動力をモータに切り替える研究が進められています。
例えば、測量や農薬散布などさまざまな用途で活用されているドローンの「先祖」は、エンジンによって大型の回転翼を動かすヘリコプタですが、高性能なモータで空を飛ばせるようになり、ドローン独自の形状が生まれました。同様に飛行機も、動力がモータに変われば、燃料用のタンクや配管、大型のエンジンなどが不要になる分、機体の形状や機内のレイアウトを一新できるでしょう。
「アウターロータ型」で新しい推進機関を
飛行機を電力で飛ばすためには、推進機関も進化させなければなりません。そこで現在、「アウターロータ型」のモータに直接プロペラを取り付ける方法が研究されています。
産業用モータの多くは、内側の回転軸に磁石、外側にコイルを配置し、回転軸から伸びたシャフトが動力を伝達します。一方アウターロータ型はコイルと磁石の配置が逆で、外側(磁石側)が回転します。そこにプロペラを付ければ、シャフトが不要なため小型化が可能です。さらに同軸上に複数のコイルと磁石を配置すれば、複数のプロペラが一方向に向けて強力な風を送り出す、新しい推進機関となる可能性があります。小型の電動飛行機なら、比較的近い未来に身近なものになっているかもしれません。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
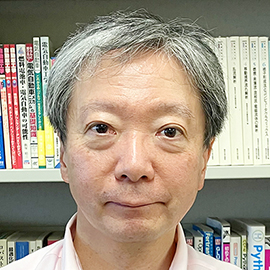
崇城大学 工学部 宇宙航空システム工学科 教授 谷 泰寛 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
航空宇宙工学、流体力学、推進工学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標7]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-7-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )


