日中戦争に対する再検討――対日協力者の立場から考える

単純ではない戦争の構図――日本に協力する中国人
日中戦争と聞くと、「日本対中国」という構図を想起しがちです。しかし正確には、「日本に抵抗する中国政府」と「日本に協力する中国政府」の政府が存在し、日本は前者と戦う一方、後者とは友好関係にありました。日本の敗戦後、日本に協力した政権は解散し、協力者は漢奸(中国語で「漢民族の裏切り者、売国奴」の意味)として、否定的に評価されてきました。しかし、なぜ彼らは日本との協力を選んだのでしょう。彼らの主体性に目を向けて背景を分析することで、日中戦争の新たな一面を知ることができるのです。
苦難の道を行く――対敵協力による局面打開
日中戦争当初、日本軍は中華民国の首都・南京を落とせば戦争は終わると考えていました。しかし中華民国は首都を重慶に移し抗戦を継続します。これに対抗して日本軍は、「中華民国」の枠組みや、当時政権を指導していた中国国民党を否定する政権を占領地に樹立しますが、中国人の支持は得られません。そこで日本が注目したのが中華民国でNo.2の地位にあった汪精衛(汪兆銘)です。汪も戦争による国土の荒廃や中国共産党の勢力拡大を憂慮し、早期和平を望んでいました。こうして汪は首都を重慶から南京に還すという体裁で新政府を樹立し、日本との提携による戦争終結、という道を選ぶのです。
「敗者の歴史」が語る歴史の本質
「歴史=過去の出来事」ですが、「過去の出来事=歴史」ではありません。無限にある過去の出来事から、重要と判断されたものが選ばれ描かれるのが歴史です。ポイントは、何が重要かは、語り手や時代・環境によって変わる点です。現在の中国では中国共産党の正統性が「抗日戦争勝利」に依拠しているため、対日協力者を客観的に評価することは困難です。一方、民主化した台湾や政治的制約の少ない日本・欧米では、漢奸の視点に立った研究が出てきています。対日協力者の研究は、歴史をより立体的に復元することはもちろん、歴史叙述の性質や国際社会を考える上でも貴重な事例なのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
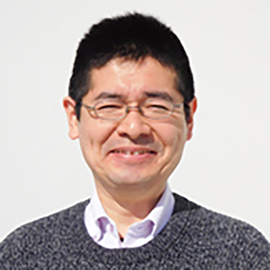
津田塾大学 学芸学部 国際関係学科 准教授 関 智英 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
歴史学先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





