人の身振りや心をよみがえらせる遺跡発掘と調査報告書
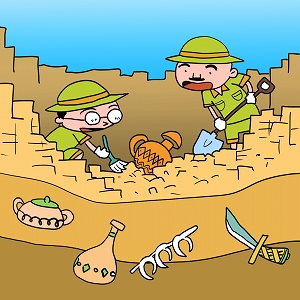
掘るだけでは終わらない
日本では年間に何千もの遺跡で発掘が行われ、発掘作業が終われば「調査報告書」がまとめられます。一度掘ったところは、掘る前の状態には戻せません。そのため、発掘現場では、3Dで再現できるほどの精度を目指して調査記録を残します。遺跡の全体像はもちろん、出土品がどのように出てきたか、掘り進めた地層ごとの状況などを詳細に記録するのです。そして、その記録を報告書としてまとめ、広く共有できるようにします。
遺跡の発掘調査報告書は宝の山
発掘調査そのものが重要なのはいうまでもありませんが、この調査報告書がしっかりしていれば、多様な研究に役立ちます。例えば古墳から埴輪(はにわ)が出土した場合、報告書を読み込んで現地の調査記録と出土品を確認すれば、断片などが出土していた状態から「この位置からこのような角度で投げられた」と推測できることもあります。古墳の地域で権力交代があって、前の統治者の古墳の埴輪をこうやって投げて割った、という結論も導き出せるのです。このように、「そこで何が行われたか」という研究もできると、出土品の破片からもとの姿を復元する先の学問的な発見にもつながります。また、自分が掘るときには「こいうことに注意しよう」と思えば、発掘作業へのフィードバックにもなります。既存の報告書には、膨大な新情報や気づきの種が眠っているのです。
報告書を読み解いて見える、古代人の心
考古学が扱うのは「人間」のことです。歴史だけでなく、さまざまな知識や関心が発揮される学際的領域です。古代の遺跡に埋められていた土器の研究例があります。それによると、素焼きのつぼを焼く際に付いてしまう黒焦げの部分を見せないように置く「配慮」が、複数の遺跡で見られたのです。これは研究者が、ほかの研究者が残した報告書を読んで、おやっと思ったことから調査して判明しました。報告書の読み込みと、現地の埋蔵文化財の資料調査との組み合わせによって、過去に生きた人々の心もまた、見えてくるといえるでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

大正大学 文学部 歴史学科 教授 冨井 眞 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
考古学、人類学、文化財学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )



