デザイン思考が切り拓く未来 「あったらいいな」を形にする力

デザイン思考でイノベーションを生む
デザインは、見た目の美しさを追求するものだと思われがちですが、課題を見つけて適切な解決策を実現するための思考法でもあります。一般的には、デザイン思考は「調査→問題定義→創造→プロトタイピング→テスト」という順序で進めるとされています。しかし近年は、「創造」から始めるアプローチが注目されています。例えば、スティーブ・ジョブズが生み出した革新的な製品は、すでにあるニーズを調査して作られたのではなく、「こういうものがあったらいい」と発想することから生まれました。創造を起点にデザイン思考を活用することで、より自由な新しいアイデアが生まれるのです。
自動車産業を支えるデザイン思考
デザイン思考が活用されている分野の一つが、人や物の移動手段である「モビリティ」です。例えば、モビリティの代表格である自動車のデザインでは、「こんな車があったらいいな」という創造から、それがどのような課題解決や新たな価値の提供につながるのかを調査・検討し、アイデアを具体化させていきます。アイデアの実現に必要な技術開発も行い、プロトタイプを作り、テストして改良を繰り返すというプロセスが、日本の基幹産業である自動車づくりを支えているのです。
「あったらいいな」から社会実装へ
デザイン思考は、アイデアを出すだけで終わるのではなく、試作して、改良を重ねることが重要です。また、デザインとエンジニアリングを融合させて、社会実装まで一貫して進めることも必要です。例えば近年、国土交通省が推進している、最高時速20キロの電動モビリティ「グリーンスローモビリティ」をはじめとする新たなモビリティの検討が進んでいます。その社会実装においては、地域に合った利用方法の検討が欠かせません。みんなで考える「こんな街になったらいいな」「この街のモビリティはこうだったらいいね」を産官学民が連携して実現していくという、デザイン思考をベースにした新しいまちづくりの方法が生まれています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
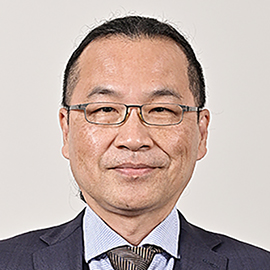





![選択:[SDGsアイコン目標7]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-7-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )








