「におい」がカギか? 認知症リスクを見いだす研究
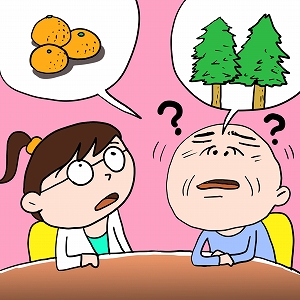
健康分野において盲点だった「嗅覚」
加齢を一因とする疾病として認知症が挙げられますが、現在この病気のリスクを早期発見する方法が確立されつつあります。そのポイントは「嗅覚」で、どのようなにおいが嗅ぎ分けにくくなるのか、嗅覚機能検査を行うことで脳の萎縮や心身機能低下が判明するとの予測です。
認知症の患者が、なぜかにおいがよくわからなくなるということは、医学界では周知の事実とされてきました。それを知った健康分野の研究者によって、理論的証明を求める研究が続けられています。その成果として、ミカンやヒノキなど植物系のにおいを判断できなくなることが、発病リスクに関わるとの見解が得られるまでになりました。
気軽な検査で健康寿命を延ばす
嗅覚機能低下は、記憶能力の不良などの自覚症状を認めない段階で、脳の萎縮を示す指標である可能性があります。嗅覚機能低下をいち早く発見することで、認知症の発症を遅らせることが可能になると考えられます。例えば、10年認知症を患うのと、3年患うのとでは、その人の人生の充実感や、周囲の家族の負担度において大きな違いがあります。
高齢者は、単純な質問が何度も繰り返される認知機能検査を嫌う傾向にありますが、嗅覚検査であればずっと気軽に行えるとのメリットもあります。あなたも、何度も精神的にストレスのかかる検査を依頼されるより、においを嗅ぐだけの検査の方が気楽ではないでしょうか?
認知症リスクが自己判断できる?
嗅覚検査はまだあまりなじみのないものですが、その効果が明確になれば、一般の健康診断の項目にも加えられる可能性があるでしょう。それがさらに浸透すれば、自分で「このにおいが嗅ぎ取れないから病院に行ってみよう」と判断できるようになるかもしれません。それこそが病気のリスク削減につながりますし、地域の保健師などの手を煩わせることなく「自分で」健康をコントロールすることにも役立つと考えられます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
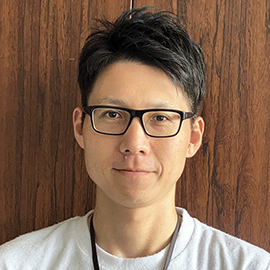
鹿屋体育大学 体育学部 スポーツ生命科学系 講師 古瀬 裕次郎 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
公衆衛生学、運動疫学、予防医学、健康学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
