ルネサンスの芸術家工房:レオナルド・ダ・ヴィンチの修業時代を例に

ルネサンスの芸術家
イタリアでは14世紀から、古代の文化遺産を手掛かりに、優れた作品を世に問う芸術家が数多く現れました。彼らの文化活動を「ルネサンス」と総称します。分野の壁を越え、万能な仕事ぶりを見せたルネサンス芸術家たちですが、その創作力の源はどこにあったのでしょうか。有名なレオナルド・ダ・ヴィンチの修業時代を見ながら、秘密の一端を解き明かします。
芸術家を取り巻く社会環境
当時のイタリアは、都市国家が乱立する不安定な政治状況でした。都市の宮廷、有力者たちがパトロンとなり、芸術家に作品を注文します。美術作品は、芸術家個人の創作物というより、注文主の意向、事情によって左右され、特定の目的で制作されました。パトロンたちが教養を高めあう環境が存在したことも、イタリアでルネサンスが花開いた要因でした。
レオナルドは、当時イタリアで一般的だったテンペラだけでなく、今日のベルギー一帯で開発された油絵技法も積極的に取り入れました。イタリア・ルネサンスの芸術家たちは、他国の文化状況に精通し、優れた点はすぐに受け入れる柔軟性を持ち合わせていました。
工房の仕組みをもとに、作品を読み解く
ルネサンス期の芸術家は、若い弟子たちを雇い入れ、その親方として工房を切り盛りしていました。一般的に弟子は14歳から20歳ごろまで修業し、組合の許可を得て独立すると、都市で工房を開くか、宮廷芸術家を目指しました。美術学校が存在しなかった当時、工房は芸術家育成の場でもあったのです。
工房では一つの作品を仕上げるまでに、親方、弟子たち、様々な人の手が関わります。研究では、親方の手がどこまで入っていたか、どの部分を弟子の誰が描いたのか、作品ごとの見極めも行われます。
レオナルドは当時、大変人気のあったヴェロッキオ工房で修業しました。ボッティチェッリも学びの場とした工房で、彼は何を修得し、親方作品に筆を入れるまでになったのでしょうか。作品を分析すると、工房内での役割分担、弟子同士の協力や切磋琢磨の様子などが浮かび上がります。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
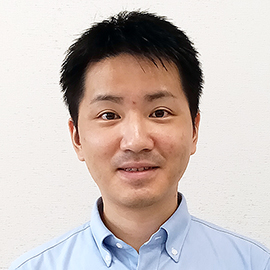
武蔵大学 人文学部 ヨーロッパ文化学科 助教 久保 佑馬 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
西洋美術史先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標10]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-10-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標16]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-16-active.png )
