ロボット競技会から生まれる、より良い社会のための実装技術
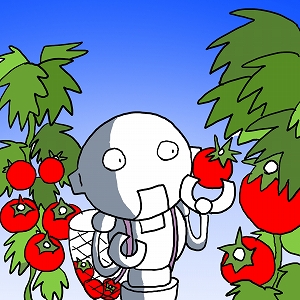
技術開発を促進する競技会
達成が難しそうな目標を掲げることで技術開発を促進するプロジェクトを「ランドマークプロジェクト」と呼びます。代表的な例に、1960年代に人間を月面に送ることを目標として実施されたアポロ計画があります。一方、ロボット研究の分野でも各種の競技会が開催されており、同様な役割を果たしています。例えば、サッカーロボットの競技会ロボカップは「2050年にワールドカップのチャンピオンと対戦する」ことを目標にしています。私たちの生活に直接関係しない目標に見えますが、多数の参加者が多様な視点からこの目標に取り組む過程から、自立搬送ロボットのための技術や照明を認識する技術などが開発されてきました。
トマトロボット競技会
具体的な社会課題をテーマとしたロボットの競技会も多数開催されています。農業分野の深刻な労働力不足の解決をめざす、トマトの収穫ロボットの競技会もその一つです。実際のトマト農場で、適切な熟れ具合のトマトをできるだけ短時間に収穫することが目標です。目標達成のためには、トマトの畝の間の移動、熟れ具合の判断をはじめとするさまざまな能力が必要です。そのために開発されたモニタリングと予測の技術は、実用化に向けて九州のトマト農場で試験運用が始まっています。
社会で活躍するロボットをつくる
大気汚染対策や化石燃料の利用削減に向けて、世界的に電気自動車へのシフトが進んでいます。しかし、充電設備を全国津々浦々に設置することは難しいのが実情です。そこで、動力源として単三充電式ニッケル水素電池6本使用する、超小型かつ軽量の一人乗り3輪以上の電気自動車の競技会が開催されています。現在は平らな道をゆっくりと走れる段階ですが、将来的には地方のモビリティとなることが期待されています。
社会で活躍するロボットをつくるには、社会課題を的確に捉えることが大切です。競技会の形でテーマを掲げることで関心が高まり、多くの人が関わることで大きなイノベーションが生まれていくのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

西日本工業大学 工学部 総合システム工学科 電気情報工学系 教授 武村 泰範 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
ロボット工学、人工知能先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?








