関心ワード「CAD(コンピュータ支援設計)」に関連する学問・研究
12件
-

白く健康な歯を守る! 患者にやさしい歯科治療最前線
関心ワード:CAD(コンピュータ支援設計)
鶴見大学
英 將生 先生- 歯の白さはオンリーワンの色
- 見た目もきれいに虫歯を治す
- デジタル技術で、より快適な治療をめざす
-

社会を変える半導体集積回路の設計
関心ワード:CAD(コンピュータ支援設計)
熊本大学
久保木 猛 先生- AIにも欠かせない集積回路
- 高速度でコスパの良い集積回路の設計
- 時間をかけてシミュレーションする
-
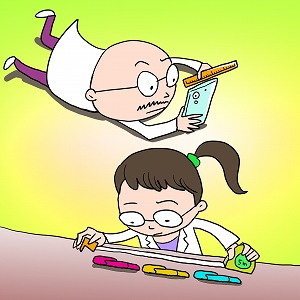
設計の重要ポイントはココ! 製造業の負担を減らす「公差」の研究
関心ワード:CAD(コンピュータ支援設計)
関東学院大学
鈴木 伸哉 先生- 設計者は誤差も計算する
- 誰でも簡単に公差を計算
- もう、たくさんの図面はいらない!
-

パラスポーツの用具開発を進化させるデジタル技術
関心ワード:CAD(コンピュータ支援設計)
広島国際大学
谷口 公友 先生- パラスポーツに必要な用具
- デジタル化のメリットと手作業の重要性
- 裾野を広げていくための取り組み
-
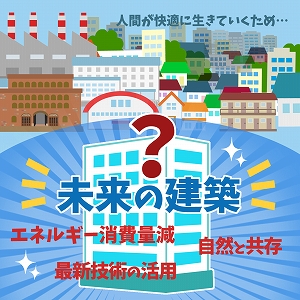
人のための建築が、ヒト以外の生態系と共存する未来
関心ワード:CAD(コンピュータ支援設計)
神戸芸術工科大学
畑 友洋 先生- 建築は環境である
- 自然と共存する姿
- 最新技術を活用して
-
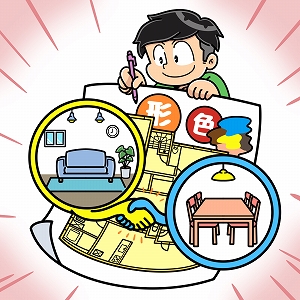
建築の設計者は、どのように空間を設計しているのか?
関心ワード:CAD(コンピュータ支援設計)
職業能力開発総合大学校
和田 浩一 先生- 設計プロセスを解き明かす
- 空間同士のつながりが大事
- プロの設計者と学生の思考を分析
-

将来当たり前の存在に? 人間のように動く「自律型ロボット」
関心ワード:CAD(コンピュータ支援設計)
創価大学
崔 龍雲 先生- リビングを片付け
- 技術を総動員
- ロボカップ@ホームで競い合い
-

建築物の設計は二次元から三次元へ~「BIM」って何だ?~
関心ワード:CAD(コンピュータ支援設計)
広島大学
中薗 哲也 先生- 建築物の設計は平面から立体へ
- 立体的な構造で「見える化」する
- これからはBIMが主流に
-

特殊な装置でリハビリテーション~歯科技工士に求められる技術~
関心ワード:CAD(コンピュータ支援設計)
東京科学大学 医歯学系(旧・東京医科歯科大学)
大木 明子 先生- 顔や顎の形が変わる患者さんをサポート
- 3Dやグラフィック作成ソフトなどを駆使
- 装置を作る技術とセンス
-

髪の断面よりも小さいナノの世界を創造する
関心ワード:CAD(コンピュータ支援設計)
長岡技術科学大学
中山 忠親 先生- ナノってなん「なの」?
- 小さい構造体こそ弱点が大きく見える
- 近年普及しそうなナノ技術の製品とは
-

将来のものづくりのキーワードは「インタラクティブ・デザイン」
関心ワード:CAD(コンピュータ支援設計)
筑波大学
三谷 純 先生- ものづくりソフト最前線
- インタラクティブ・デザインの例
- 制約の中で自由なものづくりを
-

社会に貢献するロボットの開発・実用化をめざして
関心ワード:CAD(コンピュータ支援設計)
九州工業大学
石井 和男 先生- ロボット開発を取り巻く技術環境は劇的に進化
- 実際に社会で活躍するロボット開発へ
- ロボットの自律化や安全性の確保が課題に




