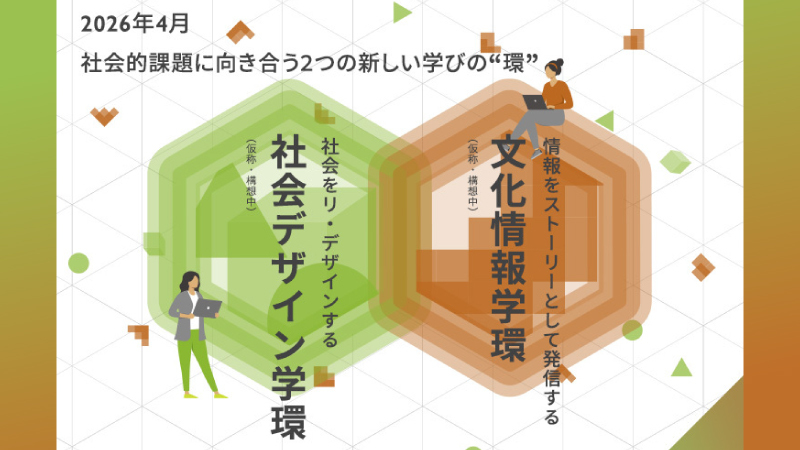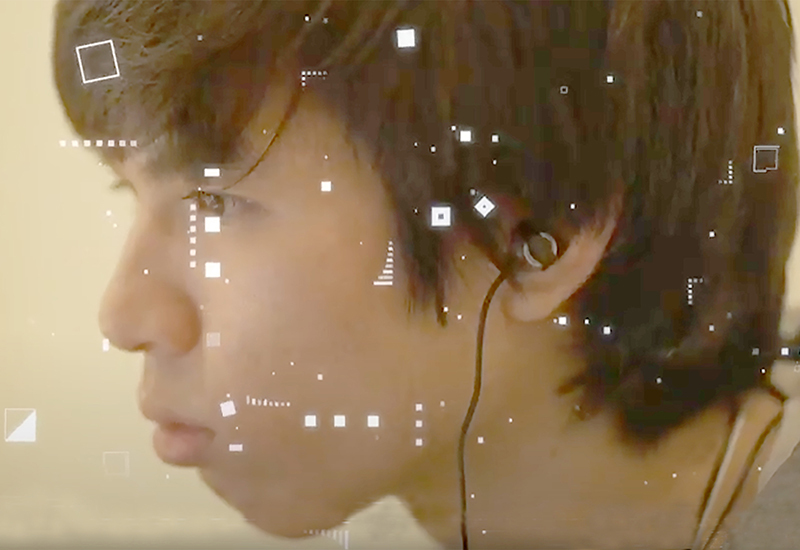「情報の力」で地域の未来をつくる人材を育てる新学類を設置
農業、環境、地域社会をめぐっては、農業の担い手不足、環境の保全と開発の調整、人口減少や少子高齢化への対応など多くの社会課題があります。こうした課題を解決して、地域のより良い未来をつくっていくためには、さまざまな「挑戦」に取り組んでいかなければなりません。例えば、効率化・省力化の推進、地域資源・エネルギーの持続可能な利用、地域内・地域間のつながりの強化、商品や暮らしのユニークさの追求などです。
一方で、現代社会では、AI、ICT、デジタル技術など「情報化」が急速に進展し、社会環境に大きな変化をもたらしています。こうした「情報化」の中で、社会課題を解決していくには、「情報の活用」が不可欠です。
農環境情報学類は「情報の活用」で地域の挑戦に貢献します。
「農」×「テクノロジー」を基礎から学ぶ

【充実した農学の基盤教育】
人のつながり、生命の循環、命の尊さを学ぶとともに、学生の自主性を促す教育プログラムを展開。共通教育(基盤教育・キャリア教育等)で培った力は、2年次以降の専門教育はもちろん、その先の人生にも必要となる「生きる力」につながります。
【学類の枠を超えた学び】
本学の2学群6学類は教育面でも深く連携しており、学生は自分の学類に限らず他学類の科目も履修できます。専門分野を超えた幅広い知識を身につけることで、学びを広げて自分の興味分野を大きく発展させることも出来ます。
【特色ある専門科目とデータサイエンス】
農業を基礎とした地域経済、地理情報システム(GIS、リモートセンシング)による情報解析及び調査・収集したデータの分析・活用に関する農学の専門的な知識と技術を身につけます。また、データの収集・整理・分析・活用の基本を学び、実際のデータを用いた演習などを通じてデータ処理スキルを習得します。
実践力と社会実装力を身につける

【アグリデザイン領域~地域におけるイノベーション人材へ~】
社会科学系の科目(農業経済学、農業政策学、アグリビジネス論など)を体系的に学び、地域産業のコーディネートや、地域の産業とその振興をマネジメントできる人材を養成します。
【地域データサイエンス領域~農業・環境分野におけるSociety5.0の実現~】
広大なフィールドを生かした地理情報システムによるビッグデータの活用方法を学び、データを用いて持続可能な社会を実現するための、コンサルタントやブリッジャー(橋渡し役)となる人材を養成します。
【充実した実践フィールド】
■約170頭の乳牛を飼育している「酪農生産ステーション」
■約80頭の黒毛和種や日本短角種、めん羊、豚、鶏を飼養する「肉畜生産ステーション」
■複合環境制御型温室での農業研究や、広い圃場で様々な農作物の栽培研究する「作物生産ステーション」
その他、北海道の農家に滞在する「学外農場実習」、企業や研究機関でのインターンシップを行う「キャリア実習」、マレーシアやモンゴルなどアジアを中心とした「海外自然環境実習」などさまざまな環境の実習先を用意。