生物の進化に関わる未知を解き明かす エピジェネティクス研究
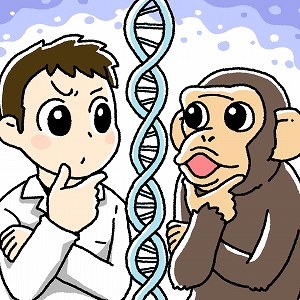
同じ遺伝子でも違う外見
人間とチンパンジーは、遺伝子の配列はほとんど同じですが外見が違います。例えば、人間はチンパンジーより頭蓋が大きく、ニューロン(神経細胞)の数も多いです。人間もチンパンジーも胎児期では神経幹細胞が細胞分裂によって増え続けますが、やがて分裂しないニューロンになります。人間の方が、細胞分裂できる期間が長いことがわかっています。その違いについて、「エピジェネティクス」のプログラムの変化との関わりの観点から研究が行われています。
エピジェネティクスとは?
エピジェネティクスとは、細胞内に含まれるゲノム(遺伝子情報)の配列を変えずに遺伝子の働きを決める仕組みで、DNAがメチル化されることなどで遺伝子が制御されています。どの細胞も同じゲノムを持っているのにそれぞれ機能が違いますが、それはエピジェネティクスのメカニズムが働くことで生じます。人は1個の細胞に60億塩基対のゲノムを持ち、その1個の細胞のエピジェネティックな情報の総体を「エピゲノム」といいます。種間での表現型の違いに、エピゲノムはどう関わっているのでしょうか。
レトロトランスポゾンが影響
研究では人間とチンパンジーのiPS細胞を使い、神経幹細胞やニューロンに分化させて遺伝子機能の違いを解析します。その結果、神経幹細胞からニューロンに変わるために重要な遺伝子の発現量が人はあまり増えないことがわかってきました。
また、人間のゲノムの半分は「レトロトランスポゾン」やその残骸でできています。レトロトランスポゾンは自身のDNA塩基配列のコピーを作り、ゲノムの別の場所に入れる活性を持ちます。人間とチンパンジーのエピゲノムを比べると、レトロトランスポゾンの挿入パターンが違うことによってエピジェネティックな状態が変化し、遺伝子をどこで使うかというプログラムが変化していることがわかってきました。
生物の進化にエピジェネティクスが与える影響については未知の部分が多く、今後も研究は続きます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?






