科学の力で「幸せ」を「見える化」する
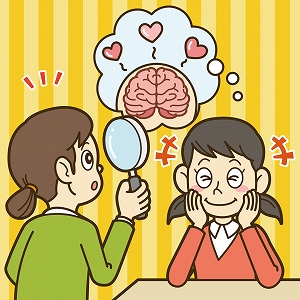
感情は体と密接につながっている
誰しも、定期テストが近づくと食欲が落ちたり、逆にうれしいことがあると食欲がわいたりといったことが起こるものです。あなたも、「うれしい」や「悲しい」「楽しい」といった感情が、体と密接につながっているのを実感したことがあるでしょう。こうしたつながりを踏まえて、体を調べることで「感情を見える化」する研究が進められています。例えば、私たちが「幸せな気持ち」になっている時、脳の中はどうなっているのかが明らかになってきました。
脳の特定の部位が活性化
MRI(磁気共鳴画像)と呼ばれる体の中の様子を見る高性能な装置の中に入った実験参加者に、いくつもの画像を見てもらいます。その上で、どの画像を見た時に幸せを感じたか、また幸せの程度はどうだったかについて答えてもらいます。すると、高い幸福度を感じた時ほど、前頭葉の少し内側の方にある「吻側(ふんそく)前部帯状回」と呼ばれる部位が活性化する(=血流量が増加する)ことがわかってきました。また、吻側前部帯状回が小さくなっている人は、あまり強く幸せを感じられないことも明らかになっています。
幸せを感じるメカニズム
実は、ある特定の遺伝子を持つ人は幸せを感じやすいこともわかっています。「幸せ」は哲学的・心理学的な問題と思われがちでしたが、いまやサイエンス(正確には生命現象を体の働きから研究する生理学など)の対象になってきたわけです。いずれ「幸せを感じるメカニズム」も解明されるようになるでしょう。
サイエンスによる「幸せ」研究が進めば、「こういう食事を取れば、幸せを感じやすい体質になる」や、「こんな運動をすることで幸せを感じる脳の部位が活性化する」といったことが当たり前の時代が来るかもしれません。幸福感は体にもいい影響を与えますから、間違いなく私たちの健康にもつながります。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標8]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-8-active.png )





