学んだ知識を組み立て、新しいものを創造する力を育てる方法とは?

年号を覚えるのが歴史学習ではない
かつて歴史の授業では、例えば「平安京に遷都したのは何年ですか」という問題に「794年」と答えることが求められてきました。しかし、現在の小学校では、単に出来事と年号を覚える歴史学習は重視されなくなりました。今、重視されているのは、その時代にどういう流れで世の中が動いたか、歴史を現代に生かせる部分はあるか、という観点です。
ブロック遊びを想像してみましょう。ブロックのピースをたくさん集めただけでは、何かの形にはなりません。それを組み上げてはじめて、車や家などの形を成すことができます。
「生きる力」を育む教育
幼稚園から高校までの教育カリキュラムの基準を記した学習指導要領は、2017年に改訂されました。小学校の学習指導要領は、学習指導と生徒指導によって「生きる力」を育むことを主眼としています。学習指導においては、ただ知識を学ぶだけでなく、学んだ知識を組み立て、新しいものを創造できる力をつけさせることをめざしています。OECD(経済協力開発機構)が実施している「国際学力調査(PISA)」で求められる、学んだ知識を実社会で活用する力を身につけ、グローバル化時代に活躍していける能力が「生きる力」です。
大事なのは「イメージ化」
小学校の教師には、難しいことをやさしく教える技能が必要です。そして、やさしいことをわかりやすく、わかりやすいことを楽しく伝えることが求められます。そのために有効なのは、「イメージ化」です。文字だけの情報に、具体的なイメージを与えることで、理解を助けるのです。例えば、歴史の年表も、単なる事実の羅列ではなく、つながりのある一つの読み物として「イメージ化」してとらえられるようにするのです。
小学校の教師は、長い時間、子どもと接し、すべての科目を教えますから、子どもの成長に大きな影響を与えます。子どもの豊かな人間性の育成に関わる難しい仕事だからこそ、やりがいもある仕事だと言えます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
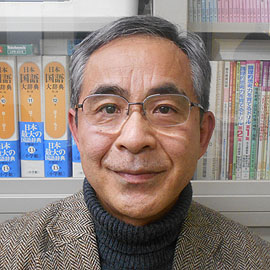
共栄大学 教育学部 教育学科 教授 光野 公司郎 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
教育学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標17]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-17-active.png )
