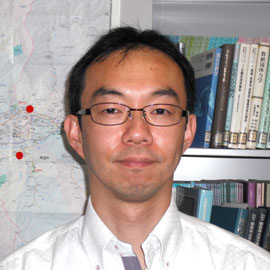避難体験VRや情報共有アプリ 住民の視点を重視した防災研究

防災に大切な住民の意識や仕組みづくり
大型台風や集中豪雨が増え、巨大地震の可能性が指摘されている中、防災関連の研究が、土木、建築、気象などの分野で盛んに行われています。
実際の災害時に命を守るには、住民一人一人の日ごろからの備えや、避難に対する心構え、地域の助け合いの仕組みが大切です。そうした観点から、住民の防災意識を高める研究や、住民がより使いやすい防災関連技術の開発につなげる研究が始まっています。技術ありきではなく、住民の視点を大切にした研究です。
ゲーム感覚で避難を体験するVR
愛媛県には、南海トラフ地震で9メートルの津波が来ると予想されている地域があります。こうした予想はハザードマップなどで周知されていますが、それだけでは実際に災害が起きた時に、自分がいる場所からどう行動すればよいかイメージできません。
そこで、その地域の中高校生と大学によって、ゲーム感覚で避難シミュレーションできるシステムが開発されました。街中の写真を撮って3DのVR空間をつくり、その中では、進んだ経路の道路が遮断されたり、津波が近づいてくるのが見えたりという映像が再現され、リアリティを持って避難を疑似体験できます。このVRを試した住民は、避難に関する知識が確実に増えているという結果が出ています。
地域の防災組織で役立つアプリ
住民が助け合う防災組織が結成されている地域もあり、そうした活動に役立つアプリも研究されています。高齢者など避難に助けが必要な人とその支援者をあらかじめ登録しておき、災害時、要支援者が避難できたかどうかを情報共有したり、応援要請したりが瞬時にできるアプリです。このアプリは地域の防災組織の防災訓練で試用され、好評を得るとともに、アプリの改善点も提案されました。また、このアプリに合わせて防災組織の在り方が見直される可能性もあります。
このような取り組みが行われることによって、災害予測や街づくりの研究がより効果的に活用されると期待されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報