楽譜の「謎」をグレゴリオ聖歌から解き明かす
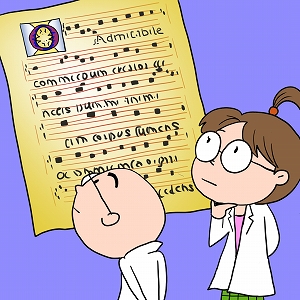
グレゴリオ聖歌の歴史
カトリックの典礼音楽として知られるグレゴリオ聖歌は、中世ヨーロッパのフランク王国が成立する過程でローマから取り入れられたと考えられています。760年頃には、ローマからキリスト教の儀式に関わる人々がフランク王国に招かれた記録も残されています。グレゴリオ聖歌は「ネウマ譜」と呼ばれる楽譜に記録されていますが、現存する最古のネウマを記した楽譜は875年のものであり、それ以前の発展過程については、いまだその多くが解明されていません。
ネウマ譜を解明
かつて、この期間のグレゴリオ聖歌は口承で伝えられてきたと考えられていました。しかし、ローマから伝わった旋律が変化を遂げながら、何らかの形で記録が残されていた可能性も指摘されています。そこで、ネウマ譜に描かれた記号の筆跡と歌詞との関係を分析し、さらに歌詞と当時の神学書に記された語句との関連を調べることで、グレゴリオ聖歌の成り立ちを探る研究が進められています。特に期待されているのが、この研究へのAI技術の導入です。テキストマイニングを活用して中世の神学文献を分析し、音の波形解析を行うソフトを用いて現代に録音された全集の音源を再検証することで、当時の歌唱法との一致点を探れるのではないかと考えられます。また、ネウマ譜の筆跡をデジタル分析することで、ネウマ譜の成立過程に関する新たな仮説が立てられるかもしれません。
音楽を再現する
グレゴリオ聖歌は、近年になって歌唱法も見直されました。50年ほど前までは、現代の音楽と同じように拍子や旋法(調性)を意識して歌われていました。しかし、研究が進むにつれて、それは本来の歌唱法とは大きく異なっていたことが明らかになり、2011年には当時の旋律を再現した楽譜が新たに出版されました。こうした解明は、当時の音楽の正しい復元にとどまらず、文化や宗教、思想を探ることにもつながります。最新技術を駆使した研究によって、今後さらにグレゴリオ聖歌の謎が解き明かされていくでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

エリザベト音楽大学 音楽学部 音楽文化学科 准教授 佐々木 悠 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
音楽学、宗教音楽学、神学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )



