レアメタルに代わる新たな触媒! 電子の力でものづくりに貢献
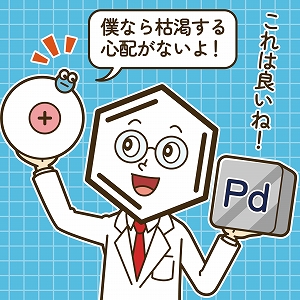
ものづくりに欠かせない炭素-炭素結合
スマートフォンの液晶画面や医薬品など身の回りにあるものの多くが、炭素同士の結合によって出来ています。特に六つの炭素原子から構成される「ベンゼン環」が複数結びつく反応は、有機化合物をつくる上で欠かせません。しかし、この反応を促すのは難しく、どうすれば簡単に実現できるのか研究が続いてきました。2010年にノーベル化学賞を受賞した研究では、パラジウムという金属を触媒として用いることでベンゼン環同士の結合をつくります。触媒とは、自身は変化せずほかの物質の反応を促す役割を持つものです。
パラジウムが抱える課題
ただしパラジウムはレアメタルの一種で、量が限られています。パラジウムが枯渇してしまうと、化学やものづくりが衰退してしまうかもしれません。また、毒性があるため、反応後に取り除く手間がかかっています。そこで、毒性が低く、自然界に豊富に存在しているものを触媒にしようと、研究が進められてきました。
偶然発見された新たな触媒
新たな触媒として、すべての原子に含まれる「電子」が働くことが偶然発見されました。鉄を触媒に使う反応を調べていた際に、鉄がなくてもベンゼン環同士が結合することが判ったのです。その研究では鉄の役割を確認するために、あえて鉄を抜いたときの様子が観察されていました。反応が進まなければ、鉄が不可欠だと証明できるからです。しかし、鉄がないときでもベンゼン環同士が結合したため、さらに詳しく調べると、電子が触媒として働くことが判ったのです。そこで、ベンゼン環に金属が結合したアリール金属とベンゼン環にハロゲン原子が結合したハロゲン化アリールを反応させると、前者に含まれる電子が外に飛び出して触媒として働いて、これらのベンゼン環の間に結合が出来ることが判りました。電子を使うことで資源の枯渇を心配する必要はなく、毒性もありません。電子触媒でベンゼン環同士を結合させる技術がさらに発展すれば、環境に優しい持続可能なものづくりや研究に貢献できると期待されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )

