人間関係も見えてくる! ネットワーク科学の可能性
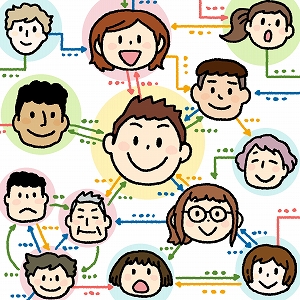
人間関係を可視化する技術
漫画や小説で、説明のために「人物相関図」が提示されることがあります。現実の人間関係も図として表すことができます。例えば、1970年代のアメリカでは、ある大学の空手クラブの34人の友人関係を2年間にわたって調査し、誰と誰がつながっているかを調べて複雑なネットワーク図が作られました。最近では、センサタグを使って誰が誰とどのくらい会話したかを自動で記録する技術も登場しており、ある高校では180人分の1週間のデータから得た会話の頻度をもとにネットワーク図が作成されました。人間関係を目に見える形でとらえる技術は進化しており、直感では見えないつながりを科学的に明らかにできるようになっています。
影響力やグループを分析
ネットワーク図が出来上がると、さまざまな分析が可能になります。まず、誰が最も影響力を持つ人物かを特定できます。多くの人とつながっている人や、影響力のある人と結びついている人などが注目されます。実際、この分析にはGoogleの検索順位を決める技術と似た原理が使われています。また、仲の良いグループの構造も見えてきます。空手クラブの例では、大きく2つのグループがあるように見えましたが、実際は4つのグループに分かれていることが判明しました。データ分析は、直感では気づけない関係性の全体像を明らかにできます。
一つの手法で広がる可能性
ネットワーク分析の手法は、分野を超えて活用できます。例えば、企業間の取引関係から重要な企業を見つけたり、遺伝子同士の関係を調べて病気の原因を探ったり、交通渋滞の原因を特定したりできます。小説『レ・ミゼラブル』の登場人物77人の関係を分析すると、物語の構造や場面ごとのグループ分けが見えてきます。このように、人やモノの「関係性」をデータとしてとらえることで、さまざまな課題に取り組めるのがネットワーク科学の特徴です。ネットワークの視点を学ぶことで、世の中を多角的に分析できるようになります。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報








