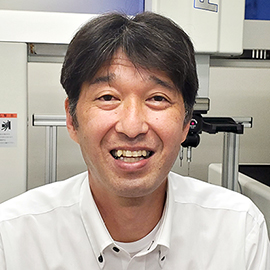なんのためにモノの表面はツルツル、ザラザラしているのか
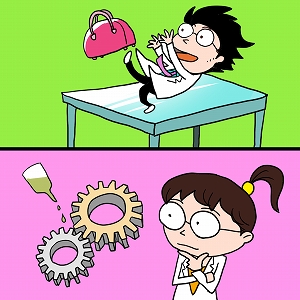
なぜ、ツルツルザラザラしているのか
表面がつるんとした質感のバッグや服は、高級感を感じさせます。テーブルの表面も、その上でものを書いたり作業がしやすいようにツルツルと滑らかです。
では、機械の場合はどうでしょうか。たいていの機械やその部品の表面は、ツルツルというより多少ザラザラしています。そうすれば機械のこすれ合う部分に油をさしたときに、細かい凹凸の間に油が保持されて滑りやすくなり、機械の動きがスムーズになるからです。これを「摺動(しゅうどう)が良くなる」と言います。表面がツルツルだとこすれ合う部分で動きが悪くなるばかりか、油をさしてもその油を弾いてしまうため、摩耗して機械の寿命を短くしてしまうのです。
摺動面の粗さは誰が決める?
機械の設計者は、表面をどの程度粗くするかを、設計図面に記号や数値で表して指定します。ただ、そうした粗さを定める基準はありません。つまり、どの素材でこのくらいの硬さの部品ならこの程度の粗さにする、といった決まった数値はなく、それは設計者やそのメーカーが持つ経験則によって決められています。表面の粗さの評価は、仕上がりの状態や見た目の品質の管理だけでなく、製品寿命や機械効率を管理する上でも大切です。そのため日本のJIS規格や、国際標準化機構(ISO)が定めたISO規格にのっとって評価されます。
精度の高い評価基準を作るために
現在、表面の粗さを測る検査に用いられている「線評価」は、同じように検査しても数値にばらつきが出るのが難点と言われてきました。そこで国際標準のISO規格において、新たに奥行きをもたせた3次元の立体的な「面評価」という新たな基準が設けられました。微細な凹凸形状など、線で評価できなかったところを評価できます。ただ、まだ現場では線評価が主流です。そこで線評価と共に面評価を組み合わせたような評価方法の普及が求められています。また摺動面の粗さの決定についても、ある程度の基準となるような指針の策定も求められています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報