どうすれば水田から発生するメタンガスを削減できるのか
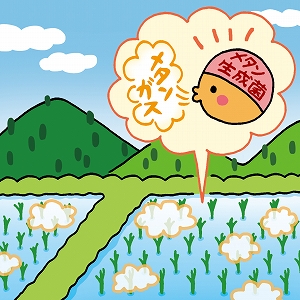
水田から発生するメタンガス
水田には前年に刈り取った稲のわら(茎葉)が残っています。酸素が豊富であれば土壌の微生物が分解してくれますが、水を張った状態が続いて土壌の酸素が少なくなると、メタン生成菌が活発化し、わらをエサとしてメタンガスが発生します。国内の農業分野から排出される温室効果ガスは約5000万tで、そのうち4割はメタンガスです。そして、水田からは約1200万tが発生しています。メタンガスは同量の二酸化炭素と比べて28倍前後の温室効果があるため、地球温暖化において軽視できない存在なのです。
積雪地域で多い排出量
水田1平方メートルあたりの排出量を見ると、全国平均は年間約20g程度、東北では約40gからそれ以上のメタンガスが発生しています。東北の水田が多いのは、「稲わらのすき込み」の時期が関係します。稲刈り直後の秋にすき込みをすれば土と稲わらが混ぜられ、微生物は稲わらを分解しやすくなります。しかし積雪のある地域で秋にすき込みをすると、混ぜた土の上に雪が積もり、田がドロドロになってしまうのです。そのため春にすき込みを行うのですが、稲わらを分解する時間が足りず、メタンガスも発生しやすいのです。
メタンガス削減のさまざまな試み
そこで考案されたのが、秋に一度、雪が降っても問題のない程度に浅くすき込みをして、春先にもう一回すき込みをする方法です。この方法により翌年のメタンガスを2割ほど削減できることがわかりました。中干し期間を長くするのも有効です。稲は育ち過ぎると穂にならない茎が増えるため、夏に田の水を抜いて生育にブレーキをかけます。その際、田の表面から酸素が供給されるため、メタン生成菌の働きも弱まるのです。この方法は温室効果ガス排出量減少を目的とした「Jークレジット制度」でも採用されており、取り組んだ農家は削減した分の温室効果ガス排出量を企業に販売し収益を得ることができます。
ほかにも、田に石灰窒素をまくことで稲わらの分解を促すなど、メタンガスを削減する試みは世界的に行われています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )


