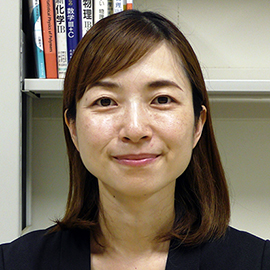「生きていること」を物理で理解する

物理的な数値で定義する
「生きている」とはどういうことでしょうか? 例えば、受精する前の未受精卵は、「生きている」と言えるのでしょうか? 哲学的にも思えるそんな疑問を、「ソフトマター物理学」の視点で測定した数値で答えようという研究があります。
ソフトマター物理学とは、細胞膜のように、固体と液体の中間の柔らかさを持つ物質の粘度や弾力、構造など物理的な特徴を調べる学問です。まずは人工的に作ったモデル細胞膜で実験を進め、徐々に実際の細胞に広げていき、何が「生きていること」を特徴づけているのかを解明するのがゴールです。
細胞膜の流動性を計測
細胞膜のベースは、リン脂質が二層になった脂質膜です。タンパク質やその他の分子が脂質膜に埋め込まれていて、お互いに作用しながら移動しています。細胞機能を担うタンパク質が、細胞膜上を漂って適切なタイミングで適切な場所に輸送されると細胞機能を起こします。タンパク質が細胞膜を漂う速度は、細胞膜の流動性によって決まります。このため、細胞膜はその複雑な構造をうまく使って流動性をコントロールし、機能発現のタイミングを制御していると考えられています。
細胞膜に見られる相分離構造を模倣したモデル細胞膜を使って、細胞膜の粘度(流動性)を測定したところ、相分離することで細胞膜の粘度が低くなることがわかりました。分子の移動速度を、細胞膜の相分離構造がコントロールしていることがわかったのです。
医師の経験知に頼らない診断を
このような研究が進んでいくことで、生き物がどのような物理現象を利用して生命活動を起こしているのかがわかってくると考えられます。
また現在は、細胞が健康か、あるいはがんなど病気の細胞かどうかは、医師の知識や経験がなければ診断できません。しかし、細胞の状態を物理的に測る技術が確立すれば、数値を見るだけで診断できる可能性もあり、医学への貢献が期待されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報