言葉の意味を理解する脳の働きを研究して、障がい者支援につなげる
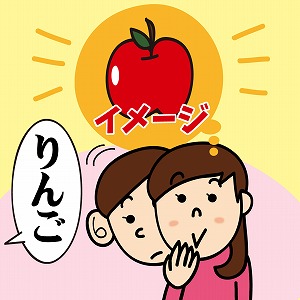
言葉はイメージと結びついている
「りんご」という言葉を聞くと赤くて丸いりんごのイメージが浮かぶと思います。このように頭の中(言いかえれば心や脳の中)で言葉が感覚的なイメージと結びついていることは意味の理解にとって重要です。例えば「りんご」と聞いても頭の中で「赤い色」「丸い形」「食べたときの味や触感」などへの連想が働かずそれらのイメージが浮かばなければ、「りんごって何?」ということになるかもしれません。
言葉の意味を理解する脳の働き
脳科学や心理学の研究によって言葉の意味を理解するときの脳の働きが調べられています。「イヌ」と聞いたら4本足の動物の視覚的なイメージを思い浮かべるでしょうか? それとも「ワン」という聴覚的な鳴き声でしょうか?
単語によっては視覚、聴覚、触覚、嗅覚など、どの感覚と関連が強いかの判断が異なります。また動作と関連が強いと判断される単語もあります。このような感覚や運動との関連の強さに応じて、単語を理解しているときに活動する脳領域が異なることがわかってきています。例えば聴覚に関連が強い単語の理解では聴覚に関連した脳領域の活動が上昇します。また動作に関連が強い単語の理解では運動に関連した脳領域の活動が上昇します。このような実験結果からも、意味理解における言葉と感覚・運動イメージとの結びつきの重要性が示されています。
言語機能の障がいの理解につなげる
「言語聴覚士(ST)」は言葉によるコミュニケーションに問題を抱える人を支援する専門職です。支援する対象は言葉の発達の遅れ、聴覚障がい、発音の障がいなど多岐にわたります。脳卒中後の失語症など言語機能に問題がある人への支援もそのひとつです。
これまでの研究で、脳の損傷領域と言葉の意味理解の低下との関係についてもいろいろなことがわかってきました。言語機能を支える脳の働きを研究して、その成果をリハビリテーションの現場に生かすことも期待されます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

東北文化学園大学 医療福祉学部 リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 教授 柴田 寛 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
言語聴覚障がい学、心理学先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?





