AIやロボットがもつ権利 多様な社会について考えてみよう
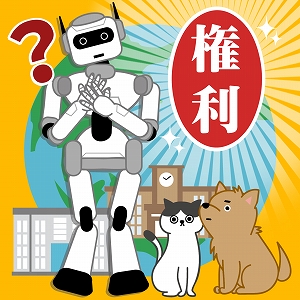
AIやロボットに権利はある?
AIやロボットの技術は急速に発展して、今や社会になくてはならない存在になっています。いろいろな職業がAIに取って代わられるとも言われますが、例えばAIやロボットを導入したことで何か問題が生じた時に、AIやロボットは責任をとれるのでしょうか。あるいは、AIやロボットに人権と同じような権利は認められるのでしょうか。
人間以外の存在の権利
現時点でAIやロボットに権利はありません。しかし世の中を見渡してみると、人間以外にも権利をもつ存在はあります。例えば会社や学校などの組織や団体は、「法人格」といって人間と同様の人格が認められており、権利・義務の主体となることができます。また、近年は動物の権利も注目されて考え方が大きく変わりつつあります。日本の民法上、動物は権利の主体ではなく「客体」としての所有物にすぎませんが、欧米を中心に広い意味での教育を通して動物は物ではないという考え方が広がり、動物の権利が認められ始めています。さらに川や土地などの自然の権利を認める国もあります。その一方で動物を殺して食べてもいいのかという論点も生じますが、これは動物の権利が認められ始めているからこそ議論される問題で、人権と同様に普遍的な権利の問題として扱われつつあることがわかります。AIやロボットの権利に関する議論は、喫緊の課題です。動物の権利や自然の権利の事例が広い意味での教育を通して参照されてさまざまな論点で議論が深まる中で、AIやロボットの立ち位置も変わっていくでしょう。
社会の構成員が増えれば
過去に女性や黒人奴隷の権利が認められたように、社会の構成員でありながら権利を認められなかった存在が、権利を認められることで社会はどんどん多様化してきました。権利が認められなければ、どんな苦しみがあっても意見を言うことすらできません。権利を認めるとは、議論のテーブルにつくということです。動物であれAI・ロボットであれ、発言する存在が多様になればなるほど、社会は豊かになるはずです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

秀明大学 学校教師学部 准教授 野村 智清 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
哲学、倫理学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標10]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-10-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標16]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-16-active.png )

