「なんとなく疲れた」を治療するには? 東洋医学と看護の共通点
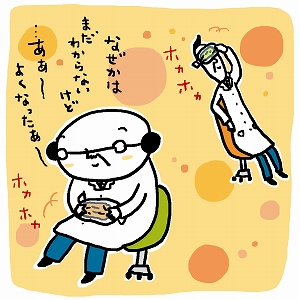
疲労を改善する治療法
疲れを感じながら生活している人は、性別や年代を問わず見られます。しかし疲労を「治療」する方法は、西洋医学や看護学ではまだ確立されていません。一方東洋医学では、「なんとなく疲れている」といった症状に向き合ってきました。よく知られているのが、はりときゅうを使ってツボを温めながら刺激を与える治療です。この治療に疲労改善効果があることは先行研究でも明らかになっています。
ほかにも東洋医学には疲労への対処法が数多くあるものの、現代の日本では西洋医学が優勢で、病院ではあまり実践されていません。特に看護の養成課程では東洋医学が必修ではないため、治療法を知らない看護師も多いのです。
東洋医学と看護の共通点
東洋医学と看護学には共通点が多いです。双方の知見を組み合わせればよりよい看護ができるかもしれません。その共通点の一つが、「患部を温める」技術が実践されていることです。例えば看護には「温あん法(おんあんぽう)」があります。熱湯にタオルを入れて絞り、それを袋に入れて患部に乗せる技術です。すると体が温まり、血流がよくなったり筋肉が和らいだりします。ただしこの方法の効果は、まだ十分に科学的に証明されていません。
「温め」と疲労の関係を探る
まずは「温める」という手法が疲労の改善に有効であることを示そうと、実験が検討されています。もし温める治療と疲労に相関関係があれば、対処の手法が増えるからです。実験では疲労度計という計測機器を用いて、交感神経や副交感神経といった自律神経の変化を観察します。自律神経は疲労を感じるとバランスが崩れます。そのため、疲れている患者を温めたときに自律神経が正常なバランスに戻るのかを分析すれば、疲労を改善する効果の有無がわかるのです。
このように看護や東洋医学で行われている手法の効果を一つ一つ検証して、「原因はわからないものの体調が悪い」といった悩みを抱える患者を救おうと研究が進められています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






