共感だけでは限界か 異文化適応能力を測る「CQ」とは?
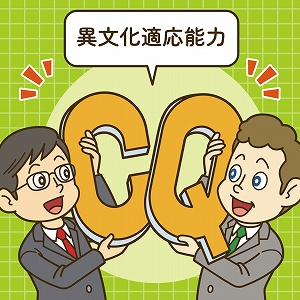
文化の異なる人同士が働くとき
経営学で研究されている「国際企業論」は、例えば、トヨタ自動車など国内外で事業を展開する企業が、グローバル経済においてどのように経営を行っているか、また、どう行えばよいのかを探究する学問です。例えば海外の労働者を雇用した場合、日本人労働者との間で争い事が起こる場合があります。そのため、国際企業論の一分野である「異文化経営論」では、企業内で異なる文化背景を持つ人々が協働する際のコミュニケーションや意見の違いに着目した研究が行われています。
異文化に「適応する力」に着目
あなたは、「異なる立場の人と理解し合うために、相手の身になって考えましょう」と言われたことがあるでしょう。そのように、異文化理解に重要なのは、共感力の指標である「EQ(エモーショナルインテリジェンス)」とみられていました。しかしグローバル社会の異文化理解において、知識を測る「IQ」、共感力を測るEQだけでは不十分なことが認識され、2000年代以降、「CQ(カルチャーインテリジェンス)」という「文化的知性」の指標が考案されました。
CQは、異文化環境における適応能力を測る指標であり、異なる文化を理解して適切に行動する力のことです。CQの研究では、企業内の多文化環境における個人の適応能力が注目され、たくさんの論文が書かれています。
相手の反応に合わせて対応できる力
CQは、認知や行動など4つの側面から20項目の質問で測定されます。例えば、行動の質問には「自分の発言を相手が理解していないと感じた時、会話のスピードを落として話しますか?」などがあります。研究では、CQが高いチームは情報の共有が円滑になり、創造性やイノベーションが促進されることが示されています。
こうした異文化経営論の研究を社員教育などに生かすことで、異文化交流だけでなく、日本人同士のチームにおいても情報共有やチームワークを強化する効果が期待されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






![選択:[SDGsアイコン目標8]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-8-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標17]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-17-active.png )

