農業の経営が変わると、地域が変わる
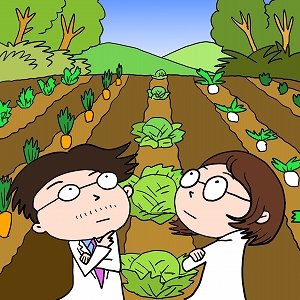
地理的観点で見る地域と農業
「住んでいる地域をもっと良くしたい」という思いや「食」の大切さは、私たちにとって普遍的なテーマです。農業は日本にとって今後も重要度が増す産業で、中でも「野菜」の生産はビジネスとの結びつきが強いものです。そこに「地理学」の観点を組み合わせると、新しい世界が見えてきます。
地理学とは地球の表面上における「差異」、つまり「地域差」をもとに、その要因を調べて事象を見ていく研究分野です。対象とする地域の、ほかとの違いは何なのか、農業の動きによって地域がどう変わっていくのかを調べるには、机上だけでなく地域と関わる必要もあります。
JAと農業法人
農業分野で調査対象となる組織は、大きく分けるとJA(農業協同組合)と農業法人の二つがあります。
JAは組合員の野菜を集荷して各地の卸売市場へ出荷するのが主な業務で、歴史や資本力があり、近年は連携や合併による大型化が見られます。日常的に使われる「産地」という言葉は、実はJAが長い時間をかけてつくってきた仕組みだと言えます。一方、近年数を増やしている農業法人は、生産農家が規模を拡大するケースや一般企業が農業に参入するケースがあり、2020年までに全国で約3万設立されました。
JAと農業法人それぞれに特徴があり、地域での特性も多様です。
消費者の求める安心・安全
農業法人の経営では、食品会社やスーパーなどの量販店との直接取引が増えます。取引を通じて消費者のニーズが生産者側に届きやすいのが大きなメリットです。結果として、近年の農業法人は、生産物の公的な制度の認証を受けたり、有機農業を増やしたりと、消費者の求める安心・安全への意識が高まりました。持続的な農業経営を認証する「グローバルギャップ」の取得にも積極的です。野菜の高付加価値化を進めることは、「産地」が変化していく要因にもなっています。こうした視点で地域を見ると、農業や農村の維持という大きな課題も見えてくるのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )








