半導体開発を加速する、電子顕微鏡の新たな技術

半導体開発に必須の電子顕微鏡解析
AIや電気自動車などの技術の進化は、半導体の進化のたまものです。今も、より高性能な半導体の研究開発が進んでいます。
それを支えているのが、電子顕微鏡を使った原子レベルでの解析技術です。条件を変えて実験を繰り返す従来の開発方法は時間がかかりますが、原子の構造がわかっていれば、条件を変えた結果が推測できて、開発のスピードアップが図れます。この電子顕微鏡での解析が、2つの新しい技術が加わることで飛躍的に進歩しました。
電子顕微鏡の誤差を補正
一つは、原子間の距離を正確に測る技術です。電子顕微鏡で半導体材料を撮影すると、原子の「点」が規則正しく並んでいることがわかります。その画像から原子間の距離が測れるのですが、画像上の原子の位置は、実は誤差があります。
そこで、電子顕微鏡の特性を調べて誤差が出る原因を突きとめ、誤差を補正する計算プログラムが開発されたことで、1000分の1ナノメートルという精度で距離が測れるようになりました。その結果、規則正しく並んでいるはずの原子の位置のズレを検出できるようになりました。このズレは、イオンのプラス・マイナスで引き合ったり反発したりするために起こるもので、そこにある電気の状態を知る手掛かりになります。
稼働中の半導体の中の原子を観察
もう一つは、稼働している半導体の中での原子の動きを観察できる「その場観察」です。電子顕微鏡では電子が通り抜けられる薄さのサンプルを使います。それに電極をつける方法、またその状態のサンプルを保持する器具を開発したことにより、従来は不可能だった「通電した状態の原子の動き」が撮影できるようになりました。
これらの解析方法で、短期間に半導体が開発できた事例もすでにあります。一例として、鉛を使わない圧電体(圧力で電圧が発生する半導体)の開発に成功しました。圧電体にはこれまで、有害な鉛が使われてきましたが、環境保護意識の高まりに応えられる画期的な材料開発となったのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
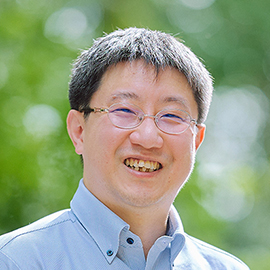
熊本大学 工学部 半導体デバイス課程 教授 佐藤 幸生 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
無機材料化学、物性化学先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?





