宇宙から災害をいち早く発見する、人工衛星の新技術
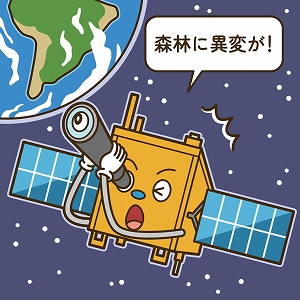
リモートセンシングで異変を感知
2025年1月、ロサンゼルスで大規模な森林火災に端を発する甚大な被害が発生しました。森林火災においては、早期に火元を発見することが被害を最小限に抑えることにつながります。
それを実現できるのが、人工衛星による「リモートセンシング」です。気象衛星や偵察衛星など、現在も目的に応じた衛星が地球上を観測していますが、衛星から異変を感知することができれば、さまざまな災害の防止や早期発見が可能となります。
低軌道か静止軌道か
地上から400~600km上空を周回する低軌道衛星からの地球観測では、地表の1m未満のものを識別できるという高い分解能(解像度)を誇ります。ただし、低軌道を周回する衛星は地球を90分で1周する速さです。特定の地点を観測できるのは一瞬で、常時観測には向いていません。
一方、地球の自転速度と合わせて周回する静止衛星なら、同じ地点を常時観測できます。ただし、静止衛星の周回軌道は地上3万6,000kmと、低軌道の約80倍も遠いため、分解能は低くなってしまいます。分解能を高くするには高精度の望遠鏡を使えばよいのですが、高精度の望遠鏡ほど大きな鏡が必要で、重量も重くなります。大きく重い物体を宇宙に打ち上げるためには、膨大な予算がかかるというジレンマがあります。
6つで1つの大望遠鏡に
そこで検討されているのが、小さな静止衛星を7つ打ち上げて、それらが六角錐のフォーメーションを組んで連携することで、大きな望遠鏡の役割を果たす、という技術です。この「合成開口望遠鏡」なら、大型の望遠鏡ほど予算を必要とせず、高い分解能で常時地球観測ができます。
合成開口望遠鏡は、各衛星の相対位置を高精度で合わせなければならないなど、実現までにはまだ課題があります。それでも今後、さまざまな災害状況や気候変動を観測するためにも、人工衛星を使った高精度の地球観測はますます必要とされるようになっていくでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






