魅せるイラストを描くには? CGとAIの融合が描く芸術の未来
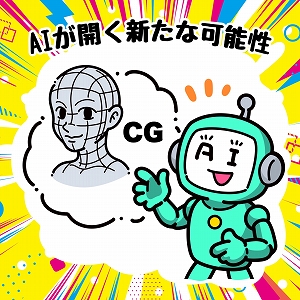
芸術と技術の進化
絵画の歴史をたどると、ルネサンス期には写実的表現が追求されましたが、写真の発明を機に芸術は大きく変化しました。写真が現実を写し取る役割を果たすことで、絵画は写実を離れ、印象派、そして抽象表現へと進化していったのです。
コンピューターグラフィックス(CG)の歴史も同様で、初期のCGは現実世界の精密な再現を追求していましたが、技術の発展とともに「非写実的表現」へと広がりを見せています。技術の進化が芸術表現の可能性を拡張し、それに対応して人間の創造性が新たな表現を生み出してきたのです。
AIが開く新たな可能性
CGも写実から非写実へと進化する中で、現在のCG研究では、立体物をアニメやイラスト調で表現する技術が注目されています。例えば、3DCGキャラクターをよりイラスト的に見せるために、顔の向きによっては、意図的にぐにゃりと変形させる手法が使われています。
さらに最近では、CGとAIを組み合わせることで新たな可能性が広がっています。人工知能(AI)は大量のアイデア生成に優れていますが、細かい表現の制御は苦手です。しかし、CGで生成した要素をAIに渡すことで、より意図した表現に近づけられます。例えば「髪を触り、笑い、かばんを持って立ち去る」という連続動作は、現在の技術ではAIだけではぎこちない部分もあるので、そんな場合はCGと組み合わせることで自然な表現が可能になります。
私たちを映し出す鏡
AIに「LOVE」という単語だけを入力すると、AIごとに全く異なる解釈の画像が生成されます。しかし、どのAIも結局は人間が作り上げた価値観や判断基準を学習しています。つまり、AIは私たちの価値観や美意識を映し出す「鏡」のような存在と言えるでしょう。芸術とは「自分を見つめ直す行為」であり、AIとの対話は私たち自身への問いかけにもなります。そしてその際、重要となる考え方があります。それは、答えは一つではないということで、自分なりの答えを見つける過程こそが、創造的な表現の本質なのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )

