インフラの点検から考古学まで―水中ロボットが活躍する未来
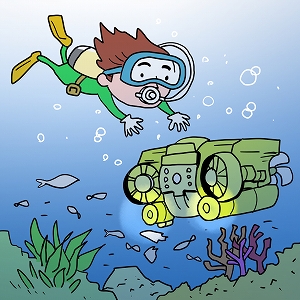
水中作業は危険な仕事
水難事故時の捜索活動、港湾やダムなどインフラの維持管理、水中における調査研究などの作業において、ダイバーは欠かせません。しかし危険を伴う仕事であり、ダイバーの数も年々減少しています。そこで、ダイバーの行う作業をロボットに代替させるための研究が続けられています。
陸上においては、ロボットやドローンが人間の代わりにさまざまな作業を行えるようになっています。しかし水中は、水流や波、水圧、低水温など、地上とは異なる過酷な環境があるため、防水・耐圧などを考えた設計が求められます。
人間と自動制御システムの共存
ロボットの操縦についても、水中では課題があります。地上では電波によってコントロールできますが、水中では電波が通じないため、リアルタイムで操縦するには船上の操縦者とケーブルでつながっている必要があります。また、水の濁りや障害物などによって視界が悪くなることも多く、操縦の難易度も高いのです。
ロボットが自律的に動けるようにすることは可能なので、観測だけを行うなら、自動制御システムで運用ができます。ただ、人間の手で行っていた複雑な作業を自律的にさせるのは技術的にまだ難しいため、現在は「触覚共有制御」と呼ばれる、人間による操縦と自動制御システムが共存した操縦法が開発されています。
水中で求められる多様な作業
ダイバーが行っている作業は、実に多様です。例えば、港湾の設備や船底などに付いているフジツボの成長度合いを確認するために、はがして肉厚を測る作業も重要なメンテナンスの1つです。また、海底や湖底に沈んでいる土器などの遺物を発掘する「水中考古学」と呼ばれる分野でも、ダイバーは不可欠です。これらをロボットができるようになれば、長時間の作業が可能となり、大幅な効率化ができます。
海洋におけるエネルギーや鉱物資源の調査、環境モニタリングなど、海洋調査は今後ますます重要になる分野と言えます。水中ロボットの活動範囲もより広がっていくことでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標14]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-14-active.png )


