「いつ始まった?」 見えない化学反応を見る観測装置の開発

合図がない反応をとらえるには?
化学反応を観察する際には、レーザー光などを使ってスタートの合図(トリガー)を出し、反応が始まるタイミングを明確にするのが一般的です。これは「過渡吸収分光」と呼ばれる方法で、関連した研究が1967年と1999年にノーベル化学賞に輝いています。しかし、自然界の反応のほとんどは、何の合図もなく時間とともに進みます。実は、こうした「トリガーのない反応」をそのまま観察する技術は、まだ存在しないのです。そこで現在、反応の前後で物質の色がわずかに変化することに着目し、それを光学顕微鏡でとらえる新しい観測装置の開発が進められています。
小さな変化を見逃さない
ごくわずかな変化を見つけるには、非常に高い精度をもつ検出装置が必要です。しかし、どんな検出装置にも「ノイズ」と呼ばれる不要な信号が混ざってしまいます。例えば、検出装置の内部では温度によって電子が自然に動き、それが本来ないはずの信号として記録されてしまうのです。こうしたノイズをどこまで取り除けるかが、この研究の大きなポイントです。プログラムを工夫して信号処理の精度を高めたり、複数の検出装置を組み合わせたりと、正確に反応をとらえる工夫が続けられています。
見えなかった反応から未来を開く
もし自然な化学反応の始まりがわかるようになれば、これまでは想像するしかなかった反応の様子が、実際に目で確かめられるようになります。例えば電池内部の反応や、呼吸による酸素と二酸化炭素の交換などが確認できれば、医薬品の開発や効率の良い電池の設計など、幅広い分野への応用につながるでしょう。また、今の教科書に記載されている化学反応は、理論や推測によって理解されてきた部分がほとんどでした。この研究により、そうした基本反応の進み方や速さが定量的に観察できるようになれば、教科書の内容が書き換わるかもしれません。見えなかった化学反応を見えるようにする研究は、化学の未来に新たな光をもたらす挑戦です。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
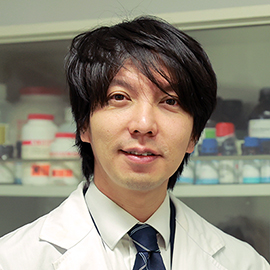





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標7]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-7-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
