動物に対し、「愛護」ではなく「福祉」を考える
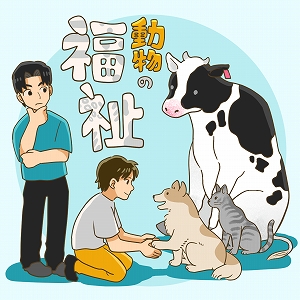
アメリカ発祥の新しい学問分野
「かわいそう」な状態にある動物を守る動物愛護とは異なり、科学的根拠を持って動物により良い生を全うしてもらおうという思想・活動が動物福祉です。その一環として、虐待や放置、災害などで生きる場所を失ってしまった動物の命について考える学問分野「シェルターメディスン」があります。
日本の獣医学は非常に発達していますが、これまでは主に病院に連れてこられた動物に提供されるものでした。しかし現在、多くの動物が保護施設、いわゆるシェルターに送られており、収容された動物の死因No.1は安楽死とされます。そこにこそ獣医学は関わっていくべきとの考えから、シェルターメディスンが始まったのです。
科学を起点に動物の置かれた環境を考える
シェルターメディスンは動物の健康維持、虐待診断、災害時の保護などにまでおよぶ、裾野の広い分野です。その中でも、特に虐待に関してアプローチする研究が日本で進められています。例えば、動物に対して虐待の恐れが見られれば、人間の場合と同じように、警察などへの通報義務が獣医師にはあります。しかし警察で虐待の有無を判断することは難しいため、動物の心身の状況把握、あるいは解剖などによって、獣医師が科学的根拠をもとに虐待か否かを判断することが求められています。
人を含めた動物の安全、健康を
動物への虐待は、人間、特に子どもなどの弱者への虐待、犯罪行為に結びつくと考えられています。つまりシェルターメディスンを考えることは、人間社会の安全確保にも結びつくのです。虐待をゼロにすることは難しくても、それを見逃さない社会をつくることは可能です。現在は、動物福祉に関する科学的データの収集・分析、また地域社会への情報発信が活発に行われています。
現実には、救うことのできない命があるかもしれません。しかし、その中から少しでも幸せな生を送れる命を増やしていくことを目標として、研究者の活動は続けられています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






