金属のふるさと、インドの鉱山開発の歴史を知る
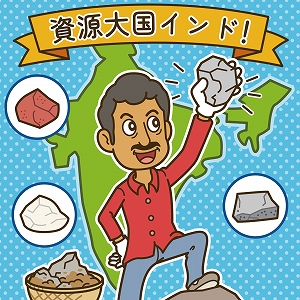
インドの鉱山資源
世界最多の人口を擁するインドは、資源大国としても知られています。鉄鉱石やボーキサイト、クロム、マンガン、石灰石や石炭など、現在の工業・製造業に不可欠な鉱物資源が国内の複数の鉱山から採掘されており、現在も増産が図られています。
歴史をさかのぼれば、鉱物資源があることは、地元の人たちにある程度知られていましたが、鉱山開発が本格化したのは19世紀以降です。イギリスの植民地となり、イギリス東インド会社を中心にさまざまな資源調査が行われる過程で、インドに豊富な鉱物資源があることがわかってきたのです。
鉱山開発の歴史
イギリス東インド会社やイギリス領インド帝国による調査は、主に現地での聞き取りによって行われ、徐々にヨーロッパで発達した測量、地誌、考古といった西洋学門の要素が加わっていきます。18世紀後半に蒸気機関が発明されると、19世紀からその原料となる石炭の本格的な調査が開始され、インド地質調査局などの組織も整備されていきました。その後は鉄道の普及によって内陸の辺境地域でも鉱山開発が行われるようになり、工業化に際して石炭の需要が拡大したことから、炭鉱開発が盛んになります。また、インド東部のオディシャー州の丘陵地では、20世紀に入って鉄の主成分となる鉄鉱石が採掘され、また製鉄に必要な石炭や石灰石も豊富であったことから、鋼鉄生産のための資源が供給されるようになりました。
金属はどこからくるのか
現在、私たちの身の回りにあるスマートフォンや家具、乗り物など、あらゆるものに鉱物由来の金属が使われていますが、これらがどのように採掘・加工され、届けられているのかはあまり知られていません。また、採掘に伴い生態系の破壊や環境汚染が発生しますが、多くの金属を輸入に頼る日本では、そのリスクや危険を負うことなく、利益を享受しています。日本から遠く離れたインドの山々で営まれてきた鉱山開発の歴史をたどることは、自分たちの安心・安全と便利な生活が、どこからもたらされているのかを知るということなのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報






![選択:[SDGsアイコン目標10]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-10-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )
