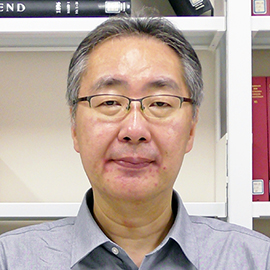社会が変われば映画も変わる? ドイツ映画が歩んだ歴史

ドイツ映画の歴史
映画は、社会を反映している文化でもあります。例えばドイツの映画産業は、社会の変化や戦争に大きく左右されてきました。第一次世界大戦中はプロパガンダのための映画が作られ、敗戦後は不安定で混乱した時代を迎えますが、映画産業は発展しました。明るい娯楽映画だけでなく、人々の不安や恐怖を刺激するような映画も作られるようになり、ジャンルの幅が広がったのです。しかし1933年にヒトラーの独裁が始まると、映画の内容が制限されました。ユダヤ人は必ず悪者として描くなど、ナチスの意向に沿わなければならなかったのです。
東西ドイツ映画の違い
第二次世界大戦後の東西分裂時代には、西ドイツと東ドイツでまったく違う映画が作られました。資本主義の西ドイツではコメディやミュージカルなどの映画が生まれました。しかし、同じような内容のものばかりが作られたため、戦後15年ほどで映画産業が停滞してしまいます。一方社会主義の東ドイツでは、映画によって国民を教育しようと、メッセージ性の強い作品が作られました。映画で描いていいものとそうでないものを、国家やソ連が明確に決めていましたが、そんな中でも厳しい条件に抵抗するような映画を生み出そうとした作り手もいました。
社会への抵抗と映画
東西ドイツでは国交が極めて制限されていたため、お互いの映画文化が交わる機会はほとんどありませんでした。それでも1960年代後半以降は「社会への抵抗」といった共通点が見られるようになります。要因の一つが、西ドイツの若い世代によって「ニュー・ジャーマン・シネマ」が生まれたことです。停滞したドイツ映画産業や社会に抵抗して始まったジャンルで、社会に生きる人々のリアルな姿を描いたものや、ナチス時代への批判など強いテーマを持った作品が見られます。革新的なことをしたい、現状を変えたいといった思いが、東西ドイツの映画産業を支えました。こうした時代を経て東西統一後のドイツ映画はどう変化したのか、研究が続いています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報