天然ゴムを「人工的に」作り出す

環境悪化につながる天然ゴムの増産
身の回りのさまざまなところで使われているゴムには、「天然ゴム」と「合成ゴム」の2種類があります。天然ゴムは「ゴムノキ」という植物の樹液(ラテックス)から作られ、合成ゴムは石油を原料とします。天然ゴムは、合成ゴムに比べて強度や弾性に優れており、例えば飛行機のタイヤや手術用手袋は100%天然ゴム製です。また、自動車用タイヤの原料も約3割が天然ゴムだとされます。しかし、ゴムノキは東南アジアを中心とした熱帯地域でしか育ちません。天然ゴムを増産しようとすると熱帯雨林を伐採することになり、地球温暖化につながる恐れがあります。
進むメカニズムの解明
こうした背景から、天然ゴムの主成分である「ポリイソプレン」を酵素的に合成する研究が進められるようになりました。まずはゴムノキの中でのポリイソプレンの生合成機構、つまり「どのように作られているのか」を解明し、実験室でその仕組みの再現が試みられています。原料は何で、どんな酵素が関わるのか、さらに酵素の立体構造を明らかにすることで、どのような酵素反応が起こっているかもわかってきました。ただし、天然ゴムは小さな分子がとても長く結合してできており、その長いつながりを人工的に作るのがなかなか困難なのです。そのため、ポリイソプレンを作る酵素と似た構造を持つ酵素をほかの植物から探して、それを用いて天然ゴムを作る研究も行われています。
AI技術の導入で研究が進む可能性も
AIの活用などもあって、近年、研究は大きく進みました。実験室で天然ゴムが人工的に作られるようになる日もそう遠くはないでしょう。もちろん、工場で大量生産できるまでには多くの課題がありますが、それもいずれは克服されると考えられます。また、こうした研究の成果はゴム製品の強度や耐久性などを高めることにもつながります。例えば、タイヤの性能が大幅に高まることで自動車の燃費が向上し、それによって環境への負荷を減らす効果などが期待されます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
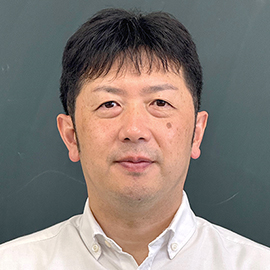





![選択:[SDGsアイコン目標12]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-12-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標13]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-13-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標15]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-15-active.png )
