対話型ロボットが普及するための課題
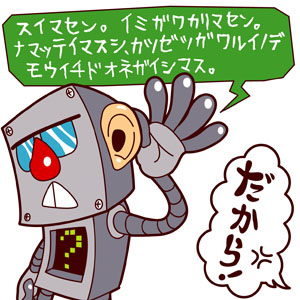
ロボットは人間の言葉を簡単には理解できない
対話型ロボットの利点は、人間が操作方法を知らなくても、ロボットを操作できることです。ロボットは人間に自分ができることを言葉で提示し、それに対し人間はしてほしいことを伝えます。しかし、ロボットが人間の言葉を理解するのは簡単ではありません。
まず、私たちの環境にはさまざまな音があります。テレビの音、BGM、会話、空調、電話の呼び出し音、チャイムの音、そのようなさまざまな音の中から、ロボットは自分に向けられた音だけに反応する必要があります。また、ロボットに向けて発せられる音声内容も同じとは限りません。「ウーロン茶を取ってこい」という命令を与える場合、人によっては「ウーロン茶」と言わず特定のお茶の商品名を言う人もいるかもしれません。「取ってこい」というフレーズも、「取ってきてくれ」と語尾を変えたり、ただ「お茶!」という場合もあるでしょう。さらに、方言やイントネーションの違いもあります。このような言い方が一定しない、多様性のある言葉を「自然言語」と呼んでいます。ロボットはこの自然言語を聞き分け、理解する能力が求められます。そこで、対話型ロボットの開発では、自然言語の「曖昧さ」や「多様性」をどう処理するかが大きな課題になります。
人間の声と非常ベルの音を聞き分ける
また、対話型ロボットが認識する対象は、人間だけではありません。例えば、対話している途中に非常ベルが鳴った場合、対話を中断して避難場所を教えるなど適切な対応が求められます。そのためには、非常ベルを警告音として認識できる機構を備えている必要があります。人間にとって、人間の声と非常ベルの音の区別は難しくありませんが、ロボットにとっては高いハードルです。しかし、それができなければ、「使える」ロボットにはならないでしょう。サービスロボットや家庭用ロボットなど、社会のさまざまなシーンでのロボット利用が期待されるなかで、音声認識技術はますます重要になると思われます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
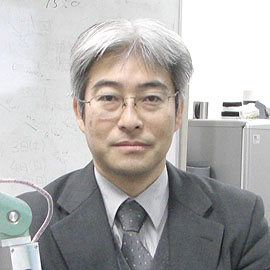





![選択:[SDGsアイコン目標9]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-9-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )
