医療にも、職人技にも! 触覚の不思議を生かした驚きのものづくり

職人技を伝えるのが難しい理由
人間の五感の中でも、「触覚」は主観的で他人との共有が難しい感覚です。その認識は、物に触れるときの圧力や振動などで起こる皮膚の変形を受け取り、総合的に判断されます。皮膚の厚さや指紋の間隔、触るときの手の動かし方、押し付ける力などが一人一人、その時々で違うため、同じものを触っても、同じ感覚を認識しているとは限りません。
触覚は、運動や作業の能力とも密接に関係しています。人は皮膚や筋肉の感覚に従って無意識に力の入れ方を調整しており、職人技を伝えるのが難しい理由もこの特性にあります。しかし触覚のメカニズムの解明により、さまざまな応用が可能です。
触感の錯覚を起こす触覚のデザイン
針金でできた網を手のひらで挟んで手を滑らせると、まるでベルベットを触っているように錯覚します。触っているもの自体ではなく、皮膚の変形がどう起こるかが触感を変えるのです。
これを応用して「触感のデザイン」ができます。これまでに、硬いプラスチック素材の表面に特殊な凸凹の形状をつけて柔らかいレザーのように感じさせるハンドルや、万年筆のような書き心地がするボールペンなどが開発されました。
他者と触感を共有できるデバイス
触感を共有する手段として開発された機器の一つが「ウェアラブル皮膚振動センサ」です。指の中ほどに巻き付けて、その指で何かを触ったときに皮膚を伝わる振動を検知します。その情報を、振動を再現する「振動子」に伝送し、それをほかの人が触ると同じ触感を共有できます。
これにより、医師の触診をインターネットで伝える遠隔診療ができるかもしれません。また、例えば体の片側にまひがある人のリハビリで、まひがある指にセンサを付けて物を触り、まひがない部分に振動子を当てて触感を感じとる訓練を行ったところ、まひした指で触感を認識でき、細かい物の操作もできるようになった事例があります。ほかにも、人と人、人とロボットの間で触感を共有し、技能の伝承や、円滑な協働作業に生かす研究も進んでいます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
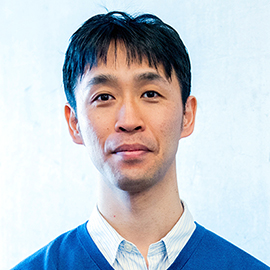
先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標8]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-8-active.png )





