牛のオスとメスはどうやって産み分ける?
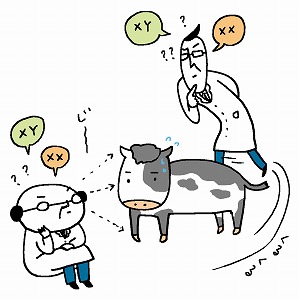
哺乳類の生殖の謎を解き明かす
生物生産学とは、動物生産や農業生産分野を研究するものです。実は哺乳類の生殖については、まだ解明されていないことがたくさんあります。その中で「なぜ動物によって一度に生まれる頭数が異なるのか?」「オスとメスがほぼ半数の割合で生まれるのはなぜなのか?」など、これら生殖の謎を解くことは、畜産において生産性を高めるための大切なファクターです。
オスとメスの産み分けに高まる期待
研究の1つに、オスとメスの産み分けがあります。ヒンドゥー教で牛は神聖な動物とされ、食べることが禁止されていますが、牛乳を飲むことは許されています。ヒンドゥー教徒の多いインドでは、肉牛は不要だけれど乳牛は欲しい、つまりメスの牛の需要が高いのです。一方、海外輸出品としても人気が高い日本の和牛はオスの需要が高くなっています。しかし哺乳類の自然出産では、オスとメスの生まれる比率はほぼ1対1です。オスとメスを分けるのは、性染色体「X染色体(メス)」と「Y染色体(オス)」です。そこで、牛を体外受精させるときに、X染色体を有する精子だけを効率的に分離して受精させられないかという研究が進められました。
X精子とY精子の機能差を利用して分離
X精子とY精子はこれまで同様の機能をもつと考えられてきましたが、実は両者には潜在的な機能差があり、X精子にのみTLR7という受容体が発現していることがわかりました。そこで精子にTLR7だけが感知するRNAウイルスの薬剤を与えると、X精子だけ動きが鈍化しました。機能差がはっきりしたことでX精子とY精子を分離しやすくなり、オスとメスの産み分けが可能になったのです。
生物生産学の観点から大切なのは、こうした研究の成果を、低コストかつ簡便な方法で実用化できるようにすることです。家畜の生産性の向上は、広くは酪農産業の活性化や、食糧難や貧困問題の解消など、社会貢献にもつながると期待されています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

広島大学 生物生産学部 分子農学生命科学プログラム 教授 島田 昌之 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
分子生物学、生物生産学、農学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標1]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-1-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標2]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-2-active.png )

