がんの薬の効果を検査で予測! 広がる「コンパニオン診断」

私たちは生涯、検査を受けている
病気やけがで病院へ行ったときに受ける検査や、健康診断で受ける検査を「臨床検査」といいます。臨床検査の目的・方法は多種多様です。例えば、心電図や超音波(エコー)検査は体を直接調べる「生体検査」です。血液や尿、組織などを取って調べる「検体検査」もあります。その方法も、機械を使って血液中のいろいろな化学成分を調べたり、患者の組織を顕微鏡で観察したり、尿などから感染症の原因となる微生物を同定したりとさまざまです。
私たちは胎児のときから亡くなるまで、いろいろな臨床検査を受けています。検査が私たちの健康を支えてくれているのです。
薬が効きそうな人を見極める
特定の薬の効果や副作用を予測できる検査「コンパニオン診断」は、臨床検査学で注目の分野の一つです。
「分子標的治療薬」は、がん細胞に特有の分子を狙い撃ちしてがん細胞をやっつける薬で、がん細胞の特定のタンパク質の量や遺伝子変異を調べるコンパニオン診断が必ずセットになっています。特定のタンパク質の量や遺伝子変異をあらかじめ検査することで、薬が効くか効かないかを予測でき、この検査結果をもとにその薬を使うかどうかを決定します。無駄な治療をせずに、その人により合った治療法を選んでいくことが可能になります。
がんの免疫療法の一つで、2018年にノーベル賞を受賞した「免疫チェックポイント阻害薬」も、同様にコンパニオン診断で効果を予測できます。
予測の確かさを高める新たな検査
コンパニオン診断は100%の予測ができるわけではなく、実際には、検査で遺伝子変異があったのに効かないケースや、変異がなかったのに効くケースがあることがわかっています。予測の確かさを高めるため、すでに使われている薬についても、効きやすいがん細胞と効きにくいがん細胞の違いをより詳しく調べて、新たな検査法の開発をめざす研究が行われています。加えて、コンパニオン診断の研究では、副作用の出やすさを見極めるために、正常な細胞への薬の影響を調べることも重要です。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
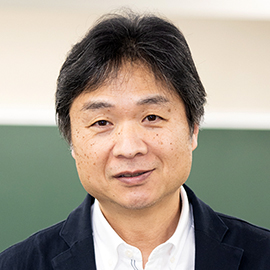
神戸学院大学 栄養学部 臨床検査学専攻 教授 竹橋 正則 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
病態検査学、臨床化学、細胞生物学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
