より手軽に、安全に! 体や運動の状態を可視化する
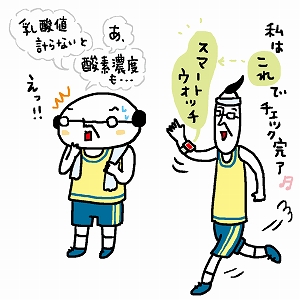
アスリートとデータ
マラソンや駅伝といった長距離走は、ランナーの体力が限界まで追い込まれるスポーツです。そのため精神力が重要ですが、それだけに頼っていては脱水症状や低血糖、ケガが起こり、能力を発揮しきることはできません。そのため、科学的な手法を取り入れることによって、より効率的な「コンディショニング・トレーニング」が行われるようになってきました。具体的には、普段から定期的に血液検査を行って貧血を未然に防いだり、乳酸値を測ってトレーニングの強度を調整したり、あるいは最大酸素摂取量を測って持久力を確かめるといったことです。
より手軽に計測する技術
こうした科学的なデータを得るための装置が大掛かりで高価であれば、なかなか活用は進みません。しかし、近年の科学技術の発達により、より手軽に体や運動についてのデータが収集できるようになりました。例えばスマートウォッチは、大きな装置や注射を用いることなく、手首に着けるだけで心拍数や血液中の酸素濃度をリアルタイムに計測でき、そこからさまざまな健康状態を可視化できます。
こうした仕組みの先駆けともいえる技術が「NIRS(近赤外分光法)」です。近赤外線の光を体にあてて、血中のヘモグロビン濃度を測定し、そこから筋肉の疲労度や回復の状態を確認できます。
医療費の削減も
ほかにも、野菜の摂取状況がわかったり、体の部位ごとの筋肉量を測ったり、さまざまなデータを取得できるデバイスの小型化が進められており、より手軽に、かつ体を傷つけることなく体や運動に関するデータが取得できるようになってきました。こうした技術は、アスリートのみに適用されるものではありません。例えば健康状態や食事をリアルタイムで管理することで、肥満や糖尿病の予防につなげることもできるでしょうし、健康に対する意識が高まることで、健康診断の受診率が改善するでしょう。特に高齢化が進み、医療費が増大し続ける日本では、こうした技術が貢献できる余地はますます拡大するはずです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

周南公立大学 人間健康科学部 スポーツ健康科学科 教授 江﨑 和希 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
運動生理学、スポーツ医学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )


