体育が苦手な先生でも、子どもの「できた!」を増やす方法
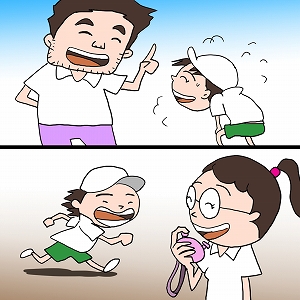
教師の行動
体育の授業においては、子どもの運動量を確保することが大切ですが、実は無駄な時間が多く含まれています。ある研究で小学校体育の授業を記録したところ、子どもが実際に体を動かしている運動学習従事時間は全体の3~4割にとどまったのです。それ以外は用具の運搬や順番待ちなどに時間を取られる傾向がありました。
また、教師による子どもへの励ましや問いかけといった「言葉かけ(フィードバック)」も重要です。言葉かけは「肯定的」「矯正的」「否定的」の3種に大別されます。なるべく肯定的な言葉かけが多くなることが望ましいのですが、教師によってばらつきがみられることもわかっています。
教材づくり
教師の行動だけでなく、「教材づくり」も体育授業の質を左右します。例えば短距離走の単元では、タイムを計測して子どもをランク付けすることが目的ではなく、少しでも速く走れるように指導することが重要です。「8秒間走」という教材は、子どもの走力によってスタート位置を調整し、8秒の間にどれだけ遠くの距離からゴールできるかに挑戦する教材です。これによって他人と比較されることなく、楽しみながら全力疾走ができます。
また短距離走においては、ある時点でスピードが落ちたり、歩幅が乱れたり、真っすぐ走れなくなる「謎の地点」が存在します。「謎の地点」は誰にでもあり、子どもの走りを記録・分析し、それを学習によって克服することが成果を高める上で有効です。
自己実現を支える
公立小学校では、基本的にクラス担任の教師が体育を担当します。スポーツが得意な教師でも、そうでない教師も、子どもが関心をもって取り組み、さらに成果も上がりやすい授業をつくっていかなくてはなりません。そこで役立つのが、前述のデータをもとにした教師の行動分析や、8秒間走のような教材です。このほかにも体育科教育の研究によってさまざまな知見を蓄え、教育現場に還元することは、子どもたちの「できた!」という成功体験を増やして、その後の子どもの自己実現を支えることにもつながるのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

盛岡大学 文学部 児童教育学科 児童教育コース 教授 盛島 寛 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
体育科教育学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )


