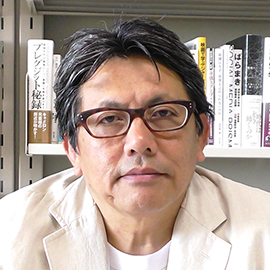コミュニケーションの視点から、政治との関りを考える
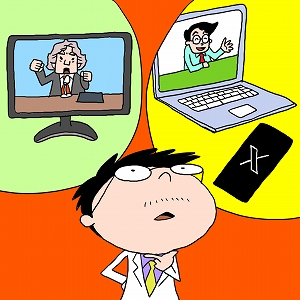
政治コミュニケーション
民主主義の誕生以来、政党や政治家は自らの考えや政策を有権者に伝えるために、さまざまなコミュニケーションを行ってきました。例えば、有権者のもとを訪れて、政策について説明し投票を呼び掛ける「戸別訪問」や、候補者が互いの政策について議論し合う「公開討論会」もその一環です。人と人とが直接対面する政治コミュニケーションは、スウェーデンやアメリカなどで現在も活発に行われています。しかし、日本では公職選挙法によって戸別訪問は禁止され、また公開討論会にもいくつかの制限が加えられています。
メディアと政治
戦後日本の政治コミュニケーションにおいては、「政治家と有権者」よりも「企業や業界が形成する団体と政党」の関係が重視されてきました。しかし、1990年代に特定の支持政党をもたない「無党派層」が急増すると、メディアを活用して、個々の有権者に向けてコミュニケーションを図ることの重要性が増します。2001年に発足した小泉内閣は、テレビを使って、「改革か保守か」「自民党をぶっ壊す」といった二元論的な単純化されたメッセージを自身のイメージと共に伝え、多くの支持を獲得しました。また2012年発足の第二次安倍内閣も、メディア戦略に注力することで長期政権を築くことに成功します。
インターネットの影響
その後はインターネットの活用が急拡大しました。主にSNSの投稿を通して自らの考えを発信する米国のトランプ大統領の戦略は、その典型といえます。一方、公正な視点で政治を報道してきたジャーナリズムは、新聞やテレビといったマスメディアへの批判の高まりとともに影響力を減少させつつあります。インターネットは関心がある情報にしか接しないような仕組みになっており、「AかBか」という二元論的な言説やフェイクニュースがインターネットを通して拡散したりもしています。
政治を巡る対立や分断が一層深刻化しつつある現代こそ、人と人とが向き合うリアルな政治コミュニケーションの価値が見直されるべきでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報