心理学で組織の課題を解決する 「組織行動論」のチカラ
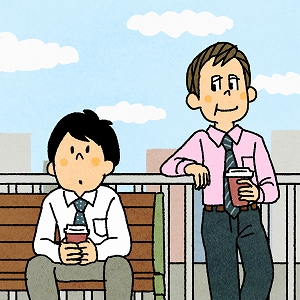
ヒトの心に寄り添っているか
多くの組織では、悪意はなくても人の心理的側面を軽視したマネジメントが行われがちです。例えば「給料を上げれば社員は頑張る」と単純に考えがちですが、実際の人の心は一律ではなく、状況によっては金銭報酬だけではやる気がでないことも多いのです。こうした人の心の機微を理解せずに組織運営をすると、施策を講じても効果を発揮しません。このような失敗を防ぐためには、心理学の知見を活用して「なぜ組織のパフォーマンスが上がらないのか」という問題の本質を探り、効果的な解決策を実施することが必要です。これを研究するのが、経営学の一分野に位置付けられている「組織行動論」です。
ビジネスの常識を覆す研究成果
心理学の研究結果はビジネスの常識を覆すことが少なくありません。例えば、仕事中にぼーっとすることは一般的には良くないと思われていますが、実はクリエイティビティは注意散漫な状態でこそ生まれることが科学的に証明されています。有名な「ダイソン」のサイクロン掃除機も、創業者が全く別のものを作っている時に偶然思いついたアイデアから生まれました。また、コミュ力のある上司がいる職場の方がクリエティブなアイデアがどんどん生まれそうに感じられますが、そのようなタイプは人の話を聞かない傾向があるため、実は内向的な上司の方が部下から創造的なアイデアを引き出せるという事実も明らかになっています。
組織の「病気」を診断し治療するための学問
こうした心理学研究の成果を活用して組織の課題を解決するためには、まず「真の課題は何か」を見極めなければなりません。医師が患者の病気を診断するように、「症状」から「病気」を特定して、適切な「治療法」を考えるのです。例えば、若手社員の離職や活気のなさという「症状」に対して、「最近の若者は●●だから」と決めつけるのではなく、調査を通じて真の原因を探り、状況に合わせた解決策を提案できるようになる。それこそが組織行動論の重要な役割なのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

武蔵野大学 経営学部 経営学科 准教授 宍戸 拓人 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
経営組織論、組織行動論、組織心理学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?








