こどもの長期入院で生じる問題、求められる家族への支援

小児看護でキーとなる存在
小児看護では、こどもを真ん中にして、家族とともに伴走しながら支援をしていきます。その中でも保護者は支援のキーパーソンです。こどもは声や表情など、さまざまな表現で自分の意思や感じていることを伝えようとしますが、その意味をとらえたり、考えていくためには、保護者の存在が欠かせません。検査や処置を乗り越えていくときに、「こうしたら頑張れるかもしれない」とこどもの力を引き出せる存在でもあります。逆に保護者が不安を感じていると、こどもも不安を感じることがあります。こどもを良い状況に導くには、保護者が良い状態であることも、とても重要です。
長引く入院の影響は家族全体に
小児がんをはじめ、長い入院が必要な病気があります。入院が長期になると保護者は働き方の変更を余儀なくされたり、経済的な影響を受けることが調査・研究によって明らかになっています。また、別の調査では、こどもの入院に付き添っている保護者の約半数が、1日のうち気分転換できる時間は30分未満と答えていました。夜間も点滴の交換で目が覚めるなど、睡眠が中断されやすく、心身への影響が大きいことがうかがえます。きょうだいも生活に大きな影響を受ける場合が見られます。
家族こそ、支援する
困難を抱えていても、保護者は入院しているこどもを優先し、自身を二の次にしがちです。また、働いている保護者やきょうだいなど、来院する頻度が少ない家族は、医療者に自身の体調や気がかりについて相談するきっかけがないこともあります。そうした家族の状況を把握して、支援につなげていくための研究が進められています。欧米では、こどもとその家族双方のための入院環境や、家族を専門的に支援する体制の整備が進んでいます。日本でも、家族が抱える不安や悩みの可視化を促すツールを作ったり、それを現場に応用していく体制を作り、支援を必要としている家族に支援が届く体制を整えて行く必要があります。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
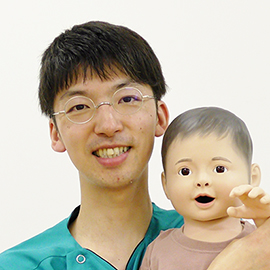





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標16]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-16-active.png )
