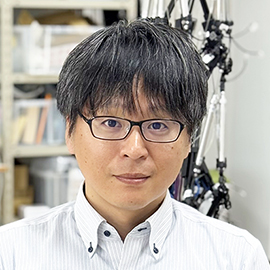生き物のように動くロボットを作るには? カギは「あえて複雑に」
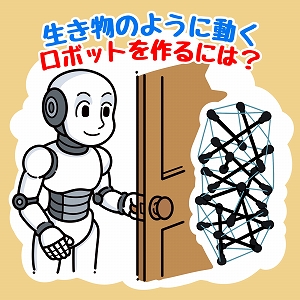
生き物のように動くロボット
現在のロボット工学では、「シンプルで正確に動く」をめざしたロボット開発が行われています。少ないパーツで構成した硬く壊れにくい構造を、正確に制御して動かすという発想です。一方で、動物は複雑で無駄なものがたくさんついた冗長な構造を持ち、柔らかく直感的に動きます。
生き物のように動くロボットを作るために、あえて、複雑さや冗長さを重視した構造や動かし方の研究が行われています。
人間の骨格・筋肉を再現
例えば、ロボットがドアを開けるとします。人間はドアノブの動かし方を全く知らないとしても、何となくガチャガチャと動かしてみながら開けることができます。しかし、モータで動かす従来のロボットは、ノブを細かく理解して、それに合わせて方向や力を制御しないと、ドアやロボット自体が壊れてしまいます。
そこで、人間の骨格・筋肉の構造を再現した空気圧で動かすロボットアームで、ランダムに回し方を変えてドアを開ける実験が行われました。ガチャガチャとノブを回す様子は人間そっくりに見えます。ただ、このアームは壊れやすいのです。なぜなら、人間の筋肉はぬめりのある膜で覆われていて、摩擦なく動くことができますが、このロボットアームは摩擦を取り除くことができないからです。
テンセグリティ構造で滑らかな動きを
人間の腕の形にこだわらなければ、摩擦を考慮しなくていいアームができます。そこで、「テンセグリティ」という構造に注目したアームも研究されています。これは、たくさんの硬い棒とひもで構成されて、ひもの引っ張る力、棒が圧縮に耐える力などのバランスで安定した形を保つものです。どこかを動かすと、全体の力のバランスがとれる姿勢に変わりますが、そのときの動きが生き物のように見えます。
この構造でロボットを作ったところ、象の鼻のように滑らかな動きをするアームができました。そして、その試行データをAIに学習させてロボットを制御させれば、適切な動きができるようになるのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。