管理会計は「従業員の幸福」を左右するシステム

管理会計は数値+心理
企業には達成すべき目標や目的があります。そこで働く全社員は、達成に向けて努力する必要があります。しかしそうした目標は、従業員には人ごととしてとらえられがちです。これを「自分ごと」として意欲を引き出せるように、企業は売上目標、原価目標などの数値目標や顧客満足度調査、在庫管理を行い、それらに対して評価をします。これを「管理会計」といいます。お金だけではなく、従業員の心理面にも良い意味でも悪い意味でも影響を与えています。このことから、「従業員の幸福」を左右するシステムともいえます。
管理会計の変遷
昭和時代(1980年代後半)までの管理会計には「お金の管理がすべて」の風潮がありましたが、それだけでは社員は成長できないと、心理面も取り上げられるようになりました。しかし1990年代は、その対象に位置付けられたのはマネージャーなど中間管理職でした。一般の従業員はお金の使い道には関与せず、指示された通りに動けばよいという考えがあったからです。しかし今の時代、現場にいる従業員が自ら動いて考えられるようにしないと企業が生き残るのは難しいということで、従業員の意欲を引き出すためにも活用されるようになりました。
時代に合わせてアップデート
管理会計は従業員の意欲を引き出すものですが、企業の業種・文化・人・もちろん時代によってその仕組みは大きく変わります。一つの企業であっても、数年たてば人が入れ替わります。目標が高すぎると従業員がついていけず離職につながることもあります。ですから管理会計も企業の「今」に合うように、カスタマイズする必要があります。
また企業は、従業員が社会の接点で自立できる場所でもあります。多様性(ダイバーシティ)が叫ばれている今、性別や障害の有無を問わず企業内で共生するために、管理会計を企業にどのように取り入れるか、評価方法や分業の仕方について研究が進められていきます。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
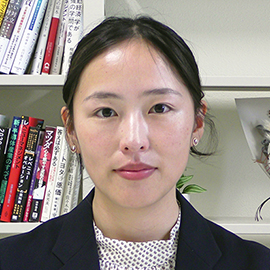





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標8]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-8-active.png )

