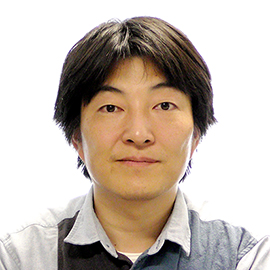100万種の細胞を作り分け! 神経回路構築の謎を解き明かす

脳が機能を獲得する仕組み
ヒトの脳には2,000億個の神経細胞があり、その種類はおよそ100万種にのぼるといわれています。これらの多様な神経細胞が、互いにつながり合って脳の機能を獲得していくメカニズムを解明するため、ショウジョウバエをモデル動物として使った発生学の研究が行われています。ショウジョウバエの神経細胞の種類は120種程度で解析しやすい上に、実験対象の視覚中枢はヒトの大脳と同じような構造をしており、発生の特徴も似ています。またライフサイクルの短さや実験系が確立されているのも利点です。
神経細胞の作り分け
神経細胞は「神経幹細胞」から作られますが、一つの神経幹細胞から多種多様な神経細胞が作り分けられるメカニズムは明らかになっていません。しかし最近の研究で、時間の経過とともに発現する遺伝子が変わることで、神経幹細胞が作る神経細胞の種類が変化していることがわかってきました。例えば、遺伝子aが発現していると神経細胞Aが作られて、次に遺伝子bが発現すると神経細胞Bが作られるといったように、遺伝子の発現がタイミングを計る時計の役割をしているのです。この仕組みによって同じ神経幹細胞から次々と異なる種類の神経細胞が作られていくと考えられますが、発現する遺伝子の切り替えはどのようにコントロールされているのかについては、研究が続けられています。
神経幹細胞を正しく作る
神経細胞を作る神経幹細胞は、発生の過程で神経上皮細胞から分化して作られますが、このタイミングが正しくないと、神経幹細胞になるための上皮細胞の数が十分でないなど、そのあとの発生が正常に進まなくなってしまいます。分化のタイミングを制御している仕組みはまだ解明されていませんが、神経幹細胞への分化の「完了」に関係する遺伝子が発見されました。この遺伝子が壊れると分化が途中で止まり、神経幹細胞になれないのです。この完了の仕組みの上流にあるのが、タイミングの制御であると考えられるため、さらに研究が進められています。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報