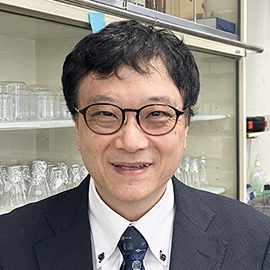妊婦の栄養状態が子どもの健康に与える影響とは?

赤ちゃんのころから生活習慣病は始まっている?
高血圧や糖尿病などの生活習慣病は、大人になってからの生活だけが原因ではありません。実は、胎内にいるときの栄養状態が、将来の健康に大きく影響することが、1980年代からの研究でわかってきました。例えば、妊娠中に栄養が不足していると、赤ちゃんの体は「栄養が足りない時代に備えるモード」になります。このとき、体に脂肪をためやすくするような働きが強くなることがあります。そのまま大人になると、栄養をとりすぎて肥満や生活習慣病になりやすくなることがあるのです。こうした考え方は、「DOHaD(ドーハッド)」と呼ばれています。2000年代の始めから、世界中でこの分野の研究が進められています。
栄養のとりすぎも赤ちゃんに影響する?
これまでのDOHaDの研究では、母親が栄養不足だった場合が主に注目されてきました。最近では逆に「過栄養」が問題になっています。近年は、妊娠した時点で肥満だったり、糖尿病を持っていたりする妊婦も珍しくありません。では、母親の体に糖が多すぎる状態で赤ちゃんが育ったら、どうなるのでしょうか? 研究では、糖の多い環境で育ったラットの赤ちゃんに、心臓が大きくなる(心肥大)や、精神的な問題が起きやすいことがわかってきました。
食事の工夫で赤ちゃんの健康を守る
こうした「過栄養」のリスクを減らすためには、妊婦の血糖値をコントロールすることが大切です。今の治療法では、血糖値を下げる「インスリン」という薬を使うことが一般的です。でも、「2型糖尿病」というタイプでは、インスリンを使っても効きにくい人もいます。そこで注目されているのが、食事の工夫です。最近の研究では、血糖値を下げる働きを持つ食品の成分として、魚の油に含まれるEPAや、牛乳などに含まれるパルミトレイン酸が効果的だとわかってきました。これらを普段の食事に取り入れたり、サプリメントで補ったりすることで、妊婦の体の栄養バランスを整え、赤ちゃんの健康にも良い影響を与えられるかもしれません。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報