「暮らしの場」である農山村地域で、観光をどう進めるか?

都市部に観光客があふれている
近年、日本への外国人観光客の増加に伴って、特定の地域に観光客が集中する「オーバーツーリズム」という言葉がよく聞かれるようになりました。観光客が集中するのは、主に都市部の観光地であるため、外国人観光客を農山村地域へと分散させるような取り組みが進んでいます。農山村地域は、昔ながらの閉鎖的な考え方があることや、観光客が殺到した場合に直接住民生活に影響が及ぶなど、都市部とは観光事情が異なります。まずは「住民の意識」を明らかにしてから、新たな取り組みや活動を考えていくことが必要です。
1軒1軒の農家民宿を「組織化」
農山村地域の観光の取り組みとして、自然に触れながら農業体験ができる「農家民宿」が各地で展開されています。雪かきや仏壇の掃除など「日本の暮らし」も体験できるため、外国人観光客からのニーズも高く、一般的には個々の民宿単位で運営されています。
その一方で、石川県能登町には47軒の農家民宿が組織化された集落があります。ここには、外国人観光客の団体受け入れのために、観光事業者との調整や開業相談などを担う事務局があります。民宿経営者の外国人観光客受入に関する意向、異文化交流への関心なども個別に考慮しながら、宿泊客の割り振り調整を行っています。農家民宿の経営者には高齢者も多く、経営の知識も乏しいため、事務局のコーディネートや経営サポートがある組織的な体制は有効だと考えられます。
まず「文化の違い」を受け入れること
各自治体の外国人観光客への観光施策についてキーワードを基に分析すると、多言語による情報案内や発信、外国人に対応できる人材の育成などは行われているものの、地域住民の異文化理解へのアプローチはあまり重視されていないことが明らかになりました。地域の生活の場で観光を進めるにあたっては、外国人観光客の文化に対する住民理解も重要です。そのため、今後は地域に在住する外国人を起用した住民との異文化交流活動なども考えていく必要があるでしょう。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報
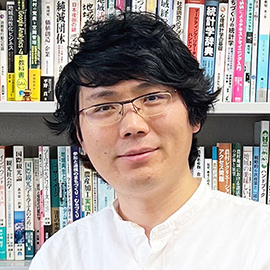
福知山公立大学 地域経営学部 地域経営学科 准教授 張 明軍 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
農村計画学、農村ツーリズム先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標4]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-4-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標8]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-8-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )


