日本の医療制度はどう作られた? 歴史から読み解く公共政策
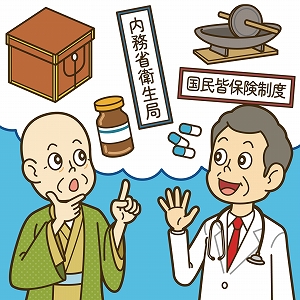
日本の医療制度
日本の医療制度は、世界的に見ても高い水準にあります。乳児死亡率の低さや平均寿命の長さは、医療の質が高く、全国的に医療サービスが行き届いていることを示すものです。一方、医療費が国内総生産(GDP)に占める割合は先進国の中でおよそ7番目であり、この数値だけを見ると、日本の医療費は高いように思えるかもしれません。しかし、日本は世界でも有数の高齢化の進んだ社会であり、高齢者の医療費が多くなるのは当然のことだと考えると、現在の医療費水準はむしろ効率的であると評価できます。誰もが一定の負担で質の高い医療を受けられるという点において、日本は「安くて良い医療」を実現しているといえるでしょう。
医療制度の歴史
現在の日本の医療制度は、最初から計画的に整備されたわけではなく、歴史的な課題や社会の要請に応じて、段階的に進められてきました。江戸時代には、病院の仕組みはなく、漢方医が自宅で薬を処方するのが一般的でしたが、明治時代に入ると西洋医学が導入され、医師制度が確立していきます。また、コレラやチフスの流行を契機に内務省衛生局が設置されて、国家として公衆衛生政策に本格的に取り組むようになりました。さらに、「富国強兵」を掲げた政府は、軍医の育成や人口増加を目的に保健師制度を導入します。そして1961年には、すべての国民が医療を受けられる「国民皆保険制度」が実現します。こうした政策が積み重なって、現代の医療制度が確立したのです。
これからの医療政策
医療制度の変遷をたどることによって、公共政策がどのように形成されて、変化してきたかを理解できます。現在、日本の医療制度は世界から高く評価されていますが、医療技術の進歩や高齢化の進行により、医療費の増大などの新たな課題にも直面しています。今後の医療政策は、これまでの政策形成の流れを踏まえた上で、時代の変化に適応していく必要があります。公共政策の研究は、こうした将来の課題に対処するための重要な手がかりとなるのです。
※夢ナビ講義は各講師の見解にもとづく講義内容としてご理解ください。
※夢ナビ講義の内容に関するお問い合わせには対応しておりません。
先生情報 / 大学情報

関西学院大学 総合政策学部 教授 宗前 清貞 先生
興味が湧いてきたら、この学問がオススメ!
政治学、政策学、医事法学先生が目指すSDGs
先生への質問
- 先生の学問へのきっかけは?
- 先輩たちはどんな仕事に携わっているの?





![選択:[SDGsアイコン目標3]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-3-active.png )
![選択:[SDGsアイコン目標11]](https://telemail.jp/shingaku/requestren/img/data/SDGs-11-active.png )






